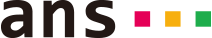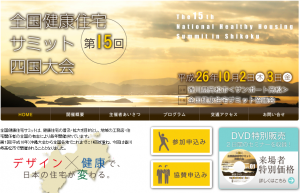未分類カテゴリー記事の一覧です
不動産と相続、早めにご相談を。
いつもありがとうございます。ansの川瀬です。
先月の終わりから今月にかけては、親会社からの要請を受けまして全国各地で「相続・不動産コンサルティング」についての講演をやっておりました。
東京から福岡、岡山、大阪、名古屋と回りまして、昨日の新潟でようやく終わりました。
不動産管理業や不動産仲介業に関わる皆様に多数お越しいただきまして、これから多くのお客様が直面する相続問題について不動産の専門家は何ができるかについてお話ししてきました。
今、この「相続」のテーマは来年1月に相続税が改正されることもあってすごく関心が高いんですね。
東京会場ではテレビ東京さんの取材も受けました。
今朝の「モーニングサテライト」という番組の中で紹介されたようです。
(残念ながら昨日宿泊した新潟にはテレビ東京系の放送局がないので見られませんでした。熊本も…ないですよね。)
「相続対策」というと一部のお金持ちの人にだけ関係があるようなイメージがありますが、そうではありません。
相続トラブルは相続税がかかるかどうかは関係なく、「どの財産を、誰が受け継ぐか?」という「遺産分割」で一番モメているのです。
中でも分けにくいのは自宅などの不動産です。相続対策とは所有している不動産について考えることだったりします。だから早めに不動産のプロに相談しておくといいのです。
家の新築を考えてansにお越しいただくお客様にも「相続」を意識されている方が増えてきました。
ansは不動産の「なんでも相談所」です。
もし何か心配なことなどがありましたら遠慮なくなんでもお聞きくださいね。
全国健康住宅サミット、講演してきました。
いつもありがとうございます。ansの川瀬です。
「あっ!」という間に前回の更新から2週間が過ぎてしまいました。サボってすみません。
この間に台風も2つもやってきたりして、激動の2週間でしたね。
さて、
10月2日、3日は、前回ご報告したとおり、香川県高松市にて開催された「全国健康住宅サミット」に行ってきました。全国から約700名もの熱心な工務店や設備業者の皆様が集まって熱気ムンムンの2日間でした。
(私は別としまして…)住宅業界では知らない人はいないような20人の著名な講師陣が各会場でセミナーをされました。
私は初日の2枠目でお話しをさせていただきました。ansのこれまでの実績を踏まえて、ansにお越しになるようなお客様がどんなことで困っていらっしゃるか、工務店はどんな対応をするべきなのか、などについてお話ししてきました。
それ以外のセミナー枠の時間帯では、私もいろんな先生のお話しを聞かせていただき、勉強させていただきました。
日本の住環境が諸外国に比べて劣悪であること、断熱性能を上げることがどれだけエネルギーの抑制につながるととともに住まい手に健康な暮らしをもたらすのかということなどなど、とても勉強になりました。
大変刺激的な2日間でした。
今、日本の住宅は省エネ断熱性能がとても向上しています。ちょっと窓や壁のグレードを上げるだけで家の性能が全く変わります。
今回、見聞した新たな知見につきましては、おいおいansの勉強会の中でも皆さんにお伝えしていきたいと思います。
乞うご期待!
全国健康住宅サミットで話をします
いつもありがとうございます。ansの川瀬です。
私、明後日10月2日(木)にちょっとした大舞台に出ます。
その舞台というのは、「第15回全国健康住宅サミット 四国大会」というところなんですが、性能が良くて健康にもいい家づくりに取り組んでいる(またはこれから取り組もうとしている)住宅会社さんが全国から500社くらい集まるようなビッグイベントなのです。
今回で15回目を迎えるこのイベント、今回は住関連の各分野の「第一人者」(←主催者さんのお言葉)を集めてセミナーや分科会を開催するようなんですが、その講師陣がすごいのです。
(私は別としましても…)住宅業界では知らない人はいないと思われるような錚々たる講師陣が約20名も一同に会します。
私のような者が光栄にもそんなところに呼んでいただいたのも、ansが住宅業界から見て関心の高い存在だからだと思います。
「健康住宅サミット」というくらいですから、講師陣は断熱や省エネ性能に取り組んでおられるような工務店経営者さんや学者さんたちが多いのですが、ほとんどは供給サイドの方々です。そんな中、私はおそらく唯一の需要サイド、エンドユーザーのみなさんの代表です。
日々、ansには「これから家を建てよう」と思っておられるエンドユーザーの皆さんがお越しになられています。皆さんそれぞれにニーズとお困りごとをお持ちです。中には住宅会社さんからひどい対応をされて傷ついておられるような方もいらっしゃいます。
エンドユーザーのみなさんは、住宅会社に何を求めておられるのか、そして、どんなことに困っておられるのか、といったことを住宅会社の皆さんにお話ししようと思っています。
参加されるのは、「健康な家づくりについて高松にまで勉強しに行こう」というような皆さんですから、真面目に家づくりに取り組んでいる方々だと思います。そういう真面目な住宅会社さんが、「いい家に住みたい」と思っておられる善良なお客様とちゃんと出会えるようになるといいなと思います。
ansは誰もが安心して住宅会社選びができるように日本の住宅購入環境をよりよくしていきたいと考えています。
そんなansの活動もお伝えしてきたいと思います。
緊張しますけど…、頑張ってきます!
9/22(月)エフエム熊本に出ます
いつもありがとうございます。ansの川瀬です。
早いものでansが熊本の帯山にお店を出してから1年半が経ちました。また今年の2月には流通団地に2号店も出すことができました。
これもひとえに熊本の皆様のお蔭と感謝いたしております。(ふかぶかと礼)
でもまだまだansの知名度は高くありません。
「ansって何やっているところ?」と聞かれることもしばしばです。
勉強会や個別相談会などに初めてお越しいただく方の中には、「何か売り込まれるのでは…」とかなり警戒しつつ、勇気を振り絞ってお越しになられる方もいらっしゃいます。
私たちは何も売り込みませんのでご安心を。
私たちは「家を建てる方々が後悔することなく安心して家づくりを進められる環境をつくりたい!」という思いでansをやっています。
そういう「思い」を拡げ、ansをより知っていただくために、私自身もCMに出たり、街中の看板に顔をさらしたりしております。
実は控えめで奥ゆかしい性格ですので本当は恥ずかしくて仕方がないのです。自衛隊前にansの看板が出ていますがその前を通る時はいつも目を伏せています。
でも「すべてはansのためだ!」と思って頑張っております。
そういう宣伝広告活動の中でも、今だに緊張するのはラジオの生放送ですね。
月に1回くらいの頻度でエフエム熊本(FMK)さんに出させていただいています。いつもわずか5分足らずくらいの短い時間ですが、なんと言っても生ですからね。緊張するんです。
話す内容として、ざっくりとした原稿はあるんですけど、MCさんが柔らかいトーンで問いかけてくださるので話しやすいのもありまして、その場で結構変わったりします。
さてそのFMKさんですが、次回は9月22日(月)、「パンゲア」という番組に出る予定です。
恐らくお昼の12時15分頃に出ることになると思います。
今回はansのスタッフも一緒に出させていただきます。生放送でいつも私がどんなに緊張してやっているをスタッフにも味わってもらおうと思います。
きっとすごく緊張するでしょうね。
さて、生放送ですのでどんな話になるのでしょうか。
宜しければぜひお聞きください。
秋のアレルギー持ちです
いつもありがとうございます。ansの川瀬です。
朝晩すっかり涼しくなりましたね。すっかり秋の気配です。
私事ではございますが、実は私、四季の中で一番苦手なのが「秋」です。
いちばん大好きな夏が終わってしまう寂しさからだけではありません。
私、「秋のアレルギー」持ちなのです。
「春先には花粉症になるから春が苦手」という方は多いと思います。それと同じように私は秋になるとだいたい鼻炎になります。春は全然大丈夫なんですけどね。
子供のころから9月~10月になると鼻炎や喘息が出たりして、楽しみにしていた運動会を休んだりしていました。
母には「あんたは寒さに弱いんだから、秋になったら暖かくしときなさい。そもそも気合いが足りない!病は気から!」とよく注意されていました。
でも、もっと寒くなる冬は全然大丈夫なんですよね。
大人になってアレルギーチェックをしたところ「イネ科の植物」がいくつかレベル3~4くらいになっていて、あーそういうことだったのねと理解した次第です。
それ以外にも「ハウスダスト、カビ、ダニ」がアレルギーレベル4です。
だから今でも、カビやホコリやダニが多く存在していそうな、古くてお掃除が行き届いていなくて結露したりしているお家に行ったりすると、目が腫れたり、鼻水やくしゃみが止まらなくなったり、呼吸が苦しくなったりします。
ややこしい人間ですみません…という感じですが、今では家の環境とアレルギーには密接な関係があることがわかっています。
家の構造や性能を良くすることで、空気がきれいに循環してホコリが溜まりにくくて結露もしないような住環境は作ることは可能です。今すごいスピードで住まいと健康の関係性の研究が進んでいます。これからの家の性能は「省エネ」だけではなくて「健康」もテーマになってくるでしょうね。
アレルギーをお持ちのお子様がいらっしゃるご家族の方は特に気になるところだと思います。アレルギー症状はアレルギーを引き起こす元(アレルゲン)から遠ざけることで症状を和らげることができます。
決して「気合い」だけでは何ともなりませんからね。
誰もが健やかに暮らすことができる住環境が整備されていくといいですね。
何がいいのかわからなくなった方に、「まずansです!」
いつもありがとうございます。ansの川瀬です。
この夏、各地で豪雨をもたらした前線が、天気予報でいつの間にか「秋雨前線」と呼ばれていました。
悲しい災害があった夏ももうすぐ終わりですね。
先週8月24日の日曜日に、いつも通りans帯山店と流通団地店でそれぞれ勉強会を開催しました。
この日は6組のお客様に新しくansに会員登録いただきました。皆様が安心して家づくりができますようansスタッフ一同しっかりとサポートしてまいります。
ansにお越しになる皆様は、「これから家づくりをしよう」とお考えになっておられるわけですが、ansに来られる動機としては大きく2つのパターンがあるように思います。
ひとつは、「これから家を買おうと思っているが、ゼロからのスタートで何もわからないので。」という方。
戸建かマンションか、新築か中古か、土地から買うか建て売り分譲にするか、といったところからの方も多く、「まずはちゃんと情報収集しよう!」というみなさんですね。ansは住宅会社さんをご紹介したり、土地を仲介したりするところですが、住宅購入に関することでしたらなんでもご相談に乗ります。ansの勉強会は注文住宅を建てる方だけでなく、中古でもマンションでもどんな方でも参考にしていただける内容だと思っています。
もうひとつは、「家を建てようと思って色々な住宅会社を回ってきたけど、もう何がいいのかわからなくなったので。」という方です。
最近はこちらの方が多いように感じます。
いつも勉強会でお話ししていますが、これは無理もないことなのです。
住宅会社・工務店さんは各社ともそれぞれの理念を持って家づくりをしています。その理念に基づいて使用する部材、仕様、デザイン、テイスト、構造などを決めて思いを込めた住宅を提供されています。みんなプライドを持って家づくりをされていますから、「ウチのこの構造、この部材、このデザインがイチバンいい!」と思っています。これは当たり前ですね。
ですので、お客様にしてみると、何社か回っているうちに「で、結局どれがイチバンなの?」となります。
これを判断して決めるのが住宅選びの難しいところですね。初めて家を建てる方は何もわからないのが普通で、いろいろなことを判断するだけの知識と情報を持っていらっしゃいません。そういう方こそ、ansでしっかり情報を整理していただければ、よりよい判断ができるようになります。
ansの理念は「すべてのお客様が、安心して、後悔しない家づくりができる住宅購入環境をつくること」です。
「あーこうすればよかった…」と後悔しないためには、「何が自分にとってベストなのか」を判断できるだけの「知識と情報」が必要になります。
私たちansが提供するのはそういう「知識と情報」です。
住宅会社とのお打合せにもスタッフは同席してサポートいたします。
「うーん、わからないな~」と思ったらansの勉強会か相談会にお越しください。
是非、ansでしっかり情報を仕入れて良い住宅検討のスタートを切っていただきたいと思います。
(久しぶりに)やっぱり「まず、ansです!」
GDP年6.7%減 10%消費増税はどうなる?
いつもありがとうございます。ansの川瀬です。
みなさん、お盆休みはいかがでしたか?
全国的に天候が悪く、雨のところが多かったですね。水害などにあわれた方もいらっしゃったのでは、と思います。謹んでお見舞い申し上げます。
さて、お盆前に大事な経済指標の発表がありましたね。
<GDP年6.8%減 反動減対策、政府に誤算 「消費税10%」判断難しく>
(産経新聞 2014年8月14日付)
『4~6月期のGDPが東日本大震災以来の下げ幅となったのは消費税増税前の駆け込み需要の反動減で、個人消費が過去最大の落ち込みとなったためだ。安倍晋三首相は7~9月期の景気動向を基に消費税率を予定通り来年10月に10%へ引き上げるかを決めるが、景気回復の先行きを見定めるのは難しそうだ。』
安倍政権は今年(2014年)の4月に消費税を8%に引き上げて、その次に来年(2015年)の10月から10%にすることを予定しています。ただその条件として、「景気の力強い回復が確認されること」というのがあります。不景気の時の増税は景気をさらに悪化させてしまう恐れがあるからですね。
その景気回復状況を測る上での代表的な指標であるGDP成長率ですが、1月~3月は消費増税前の駆け込みもあって年率換算6.7%と大幅に増加しましたので、4月~6月はその反動で消費が落ち込んで悪い数字が出るだろうとは予想されていました。
注目されていたのは、「その落ち込みはどれくらいになるのか?」というところ。
増税前と増税後の山と谷を考えると、1月から6月までを合算して「マイナスにならないライン」というのがひとつの目安、つまり1月~3月が6.7%増でしたから4月~6月に6.7%減以上か以下かというのが評価の分かれ目だったわけですね。
「5%以下の減」程度であれば、「景気の谷は浅かった。景気は回復している」という判断になり、10%増税がほぼ決定的になったでしょうし、「8%以上の減」程度になったら、「景気の谷は想定以上に深かった。景気は回復していない」となって消費税10%増税の見送りムードが強まったかもしれません。
それが結果は、「6.8%減」。
1月~6月までトータルでほぼゼロ成長という結果になったわけです。
なんとも判断が難しい微妙なラインになりましたね。
さて、この結果を受けて今後の経済政策、そして消費増税判断はどうなっていくでしょうか?
甘利経済財政大臣は強気です。
「消費税判断は今後7~9月の状況を含め、できる限り経済指標、雇用統計などの資料を揃え、最終的に首相が判断する。」とした上で、「月次指標をみても景気は緩やかな回復基調が続いており、これまで政府が示してきた景気認識に変わりはない。具体的な数字は断定できないが、先行きには明るいイメージを持っている。」と発言しました。
これだけ強気になれるのは、「最近の経済指標が良くなっている」ということがあるでしょうね。
確かに最近の報道を見ていると、日本企業の業績は良くなっているし、賃上げも進んでいるようです。リーマン直後は5%を超えていた失業率も約3.5%まで下がり、ほぼ完全雇用レベルに近付きつつあります。
物価についても5月の消費者物価指数は前年比3.4%の上昇で、2%の消費増税の影響を考えても1%以上の上昇、すでに半年以上にわたって1%以上の上昇が続いています。
さてさて、日本の景気回復はホンモノなんでしょうか?
おそらく政府は「増税したい」と思っているでしょうが、まだはっきりとは言えない状況になっています。
消費税が増税されるかどうかは、7月~9月のGDPがどれくらいのプラスになるか、特に消費がどこまで回復するか次第になってきました。
おそらく7月~9月GDPの発表は11月中旬ごろでしょうから、10%に消費増税するかどうかは11月下旬~12月上旬ごろに安倍総理から発表されるのではないかと思います。
家を建てようかなと思っている皆さんも気になるところですよね。
引き続き注意して見ていきたいと思います。
子供に寛容な社会がいいですね
いつもありがとうございます。ansの川瀬です。
みなさん台風11号は大丈夫でしたか?
私、相変わらず移動が多いので飛行機が飛ぶかどうかヒヤヒヤしていました。
移動と言えば、最近は夏休みに入ったこともあって、いつもはビジネスマンしかいない新幹線や飛行機に家族連れが増えてきました。
私には、もう大きくなりましたが、2人の子供がいるので全く気にならない(むしろ微笑ましい)のですが、中には子供が気になる方がいらっしゃるようです。
先日、まずまず混んでいる新幹線の中で、私の前の列のシートに小さなお子様2人を連れたご家族が乗っておられました。3歳くらいの男の子は元気にはしゃぎ、1歳になるかどうかの下のお子さんはずっと泣いていました。
すると、私の後ろの席から「うるさい!静かにさせろ!」という怒鳴り声が…。
お母さんが前のシートから顔を出して、振り返って私に「すみません…」と。
いやいや私ではないですよ、と手を振りましたが、お母さんすぐ顔を引っ込められました。
私の子供も小さかった頃は大変でした。
泣くし、叫ぶし、走り回るし。随分手を焼いて、周りに謝ってばかりいました。混んでいる電車に乗るのはいつも躊躇したものです。
子供があまり好きではない人が眠くて仕方がないときに、周りで子供が泣いていたり走り回ったりしていたらイライラするのもわからないでもありません。
「子どもは仕方がないにしても、静かにさせない親が許せない」と思っておられるのかもしれません。
いやー、でもなかなか静かになりませんよ。
赤ちゃんに「静かにして。泣かないで。」といくら言っても無理ですし、3歳くらいの子は大好きな家族みんなでかっこいい新幹線なんか乗ったらそりゃテンションも上がるでしょう。叫んでどこまでも走り出したくなるのも無理もありません。
真面目なご夫婦ほど子ども連れでの旅行やレストランでの食事などを躊躇されます。
でも、世の中みんなが外食したり旅行したりする方が景気だって良くなります。
子供は日本の宝。
これからの日本を支えて、私たちの老後の年金や健康保険料を負担してくれる世代です(←都合よく考えています)。
個人的には子供連れには広く寛容な社会であってほしいと思いますね。何より、笑ったり、泣いたり、怒ったり、感情をそのまま出す子供って可愛いです。
ちなみに、ansにはキッズルームもありますし、スタッフがお子様を見守りますので安心してお越しください。
私は顔がコワイのか子供にはあまり好かれませんが、私自身は子供好きです。
私は子供に「静かに!」とはゼッタイ言いませんのでご安心を。
工務店経営者の皆様との会議
いつもありがとうございます。ansの川瀬です。
猛暑ですね。皆様、熱中症にはくれぐれもご注意を。
さて、私、この猛暑の中、ここ2週間は全国の工務店さんの「経営者会議」に出ておりました。九州・熊本からスタートして、中四国、関西、中部・東海、南関東、北関東・東北信越と巡ってまいりました。各会場20~30社くらいの工務店経営者の皆様にお集まりいただきまして、今後の住宅会社経営について、熱く(暑苦しく)語り合ってきました。過去何度かやっている企画ですが、今回はいつも以上に経営者の皆さんの意識の高さを感じました。
先日、野村総研さんが住宅市場の見通しを発表されました。それによると、今現在、1年間で約95万戸の新築住宅が建設されていますが、それが2020年度には約65万戸くらいになるのではないかと予測されています。背景にあるのは人口の減少ですね。
住宅産業においては、市場が向こう5~6年で4割ほど小さくなるわけです。
これは死活問題です。
「いずれはそうなる」というのは誰もが何となくわかってはいたのですが、いよいよそれが現実感を持って間近に迫ってきたな、という感じです。
来年に消費税が10%になるとすると、もしかしたら昨年8%に上がる前の時のように駆け込み需要が起こるかもしれません。そうするとにわかに目先の仕事が増えて忙しくなり、5~6年先の市場の縮小への危機意識は薄らいでしまうかもしれません。でも市場の縮小は現実に起こることです。そこから目を背けずに、着々と準備をする必要があります。
市場縮小がほぼ明らかな今、5年先、10年先を見据えて今、工務店経営者は何をするべきか?
そんなことを皆さんと語り合ってきました。
いつも思いますが、工務店経営者の皆さんってホントに真面目ですね。
「家」という、家族の暮らしの基盤であり、財産と健康にも大きくかかわる「一生モノの資産」を創っているんだ、という自負と責任感があります。私も住生活に関わる仕事をしている者として刺激を受けましたし、身の引き締まる思いでもありました。
全国の工務店経営者のみなさま、ありがとうございました。
私も頑張って自分の出来ることを精いっぱいやろうと思います。
将来不安から目を背けないこと
いつもありがとうございます。ansの川瀬です。
もう間もなく梅雨明けですね。蒸し暑さの中に、時折真夏の激しい日差しが降り注いできます。皆さまもどうぞ夏バテにはお気を付けください。
さて、先週末は新潟におりました。(新潟も30度以上あって暑かった~)
不動産資産家の方に向けて不動産投資のセミナーをやってきました。ansを始めてからはセミナー講師といっても住宅関連の話が多かったので、「不動産投資」のテーマは久しぶりです。ですのでセミナー内容をイチから考えて準備をして臨みました。
セミナーの準備をするときは、まずセミナーの起承転結を考えまして、それぞれのパートの関連データを集めて分析して「言いたいこと」を整理します。今回は30~40代の若い方もいらっしゃるということでしたので、まず「起」のところで「そもそもなぜ不動産投資なのか?」ということを話そうと思いました。
不動産投資をする動機には大きく3つあると言われています。
①相続税対策、②固定資産税対策、③収益対策
中でも若い方にとっては③の「収益対策」がもっとも関心の高いところだと思います。
その背景にあるのは「将来の収益不安」ではないでしょうか。
年金制度への信頼が揺らぐ中、どのように自分で財産を形成しリスクに備えるか。働いて財産を形成しようにも、給与が上がっていく保証もないし、定年まで働けるかも退職金がいっぱい出るかもわからない。
そんな時代に備えて生き抜くるためにも投資を考えたい、ということだと思います。
例えば「老後」です。データを集めて調べるとよくわかりますが、私たち40代より下の世代の老後はかなり厳しい現実が予想されます。「こりゃ早めに投資のひとつやふたつはやっておかないと大変だな」とつくづく思います。
よく40歳前後の方に次の3つの質問をします。
「老後の生活はいくらかかると思いますか?」
「その老後は何年続くと思いますか?」
「年金はいくらもらえると思いますか?」
皆さん、自分の認識と現実の差の大きさを知ると、驚かれて、その後、暗くなられます。
でも知らなかったわけではなくて、本当は何となくわかっていたことなんですね。目を背けていただけと言ってもいい。
まずは現実を正しくとらえることからですね。老後を迎えた時にジタバタしても怒っても泣いてももう遅いですからね。
ansに来られる方々の多くはもう一段お若い方々が多いですが、家を建てるのも大きな投資と言えます。将来のライフプランをよく考えてから、どういう家をどれくらいの価格で建てるのかを決めた方がいいと思います。
私たちは大変な時代に生きていますね。頑張っていきましょう。
新しい投稿ページへ古い投稿ページへ