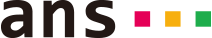未分類カテゴリー記事の一覧です
住宅購入環境は整っています
いつもありがとうございます。ansの川瀬です。
少しずつ春めいてきましたね。あと少しで春到来です。
さて、4月になるといよいよ消費税が増税されます。
他の業界では最後の駆け込み販売が行われていますが、住宅業界ではもうとっくに駆け込みは終わっています。
それどころか住宅業界ではすでにその反動減まで起きています。
↓↓↓
<注文住宅止まらぬ反動減 2月受注額 大手2ケタ減>
(日本経済新聞 3月10日付)
『大手住宅メーカーの2月の受注速報が10日、出そろった。最大手の積水ハウスが前年同月比32%減になったのをはじめ、大和ハウス工業は10%減、住友林業、パナホームもそれぞれ16%減、19%減と減少幅が広がった。ミサワホームも棟数ベースで26%減と各社とも反動減に苦しんでいる。消費増税前の駆け込み需要の反動が続き、受注回復には時間がかかりそうだ。』
大手住宅会社さんにとってはちょっと想定以上の落ち込みのようです。この落ち込みが長引くとマズイ!ということで、4月以降には各社挽回するための販売促進策を出してきそうです。
消費増税に合わせて4月からは住宅ローン減税の拡充やすまいの給付金制度などがスタートします。ある年収層の方には消費増税後のこれから家を建てた方がお得になるケースもあります。また消費増税後の景気落ち込みを防ぐために金融緩和は続きそうですので、住宅ローン金利も低位安定しています。
「慌てずじっくり考えます。」という方は今多いと思います。住宅会社もここ数か月忙しかった建築現場が落ち着いてきました。4月以降には互いに腰を落ち着けて商談が出来そうですね。
住宅会社の販促キャンペーンなども始まりそうですし、これから建てる人にとっては実は良い環境が整っていると言えそうですね。
さあ、ansでしっかりお得な家づくり情報をキャッチして後悔しない家づくりをなさってください。
ans勉強会の予定は、ホームページ「勉強会予約」で確認ください。
「都合が合わない」という方は「相談会予約」にどうぞ。
お待ちしています。
どうなる相続!?どうする不動産!?
いつもありがとうございます。ansの川瀬です。
先週金曜、大阪にある不動産会社さんに研修をしに行ってきました。
研修の内容は「相続・不動産コンサルティング」。
土地や自宅、収益アパートなどの不動産をお持ちの方が相続に備えるにあたり、不動産のプロの立場からどのように相談に乗って助言業務を行っていくかという研修です。
最近はこのテーマで不動産会社のみなさんに研修をすることが増えてきました。
背景にあるのは、 いよいよ2015年1月に施行される「相続税の改正」ですね。
この改正で相続税が実質増税になることから、テレビや雑誌などでも相続をテーマにトラブル事例などが頻繁に取り上げられるようになっていますよね。
「自分の場合は大丈夫だろうか?」「相続税はいくらになるのだろうか?」「どのように不動産を相続させたらいいのだろう?」というような不安を持たれている方が増えています。
相続はする側にとっても、受ける側にとっても法律や税制など難しいことが多いと思います。
中でも相続で一番困るのは自宅や遊休地、大きなアパートなどの「不動産」の扱いです。
複数の相続人がいるときにどの資産を誰にどれくらい相続させるのかという、いわゆる「 分割」はもっともトラブルの種になるものです。ひとつしかなくて分けられない不動産を巡って兄弟が大モメにモメる、なんてことはよくある話です。
相続トラブルとは「相続税トラブル」ではなく、「資産分割トラブル」なんですね。
日本人が保有する資産の約7割は不動産です。
つまり相続とは「一番大きな資産である不動産をどう評価してどうわけるか?」ということにかかっているわけですね。
では、その難しい相続問題をいったい誰に相談するべきなのでしょう?
野村総研さんの調査によると、相続を相談する相手は、1位が税理士さん、2位が弁護士さん、3位が金融機関となっています。
でも、 税理士さんは税制のプロですが、不動産のプロではありません。
弁護士さんは法律と紛争処理のプロですが、こちらも不動産のプロではありません。
不動産を持っている方が相続について最初に相談する相手は、本当は『相続に詳しい不動産のプロ』であるべきなんです。
だから、相続税改正で相続に関心を持つ方が増えている今、身近な相続相談所になるべく不動産会社さんが相続相談の勉強をし始めているんですね。
「相続相談はお近くの不動産屋さんで」という時代になってくると思います。
ansにも住宅の建て替えやリフォームを考えておられるシニア世代の方からよく相続の話が出ます。
不動産と相続は切っても切れない関係にありますからね。
そこで、ちょっと早い告知ですが、恒例になってきた次回のans相続セミナーを4月12日(土)ans流通団地店にて開催することにしました。ぜひこの機会に相続と不動産についてしっかり学んで、安心かつ円満、しかも損をしない相続を迎えていただきたいと思います。
詳細が決まりましたらまたホームページ上でご案内します。
相続なんて関係ないよ、という方はひとりもいらっしゃいません。誰もが学んでおくべきテーマです。
みなさんのお越しをお待ちいたしております。
真面目な工務店と真面目なお客様、なぜトラブルに?
いつもありがとうございます。ansの川瀬です。
お陰様で2月22日、無事にans2号店となる「流通団地店」がオープンいたしました。
多くの皆様に祝福していただき感謝の気持ちでいっぱいです。
早速、家づくりを検討しておられたり、土地を探しておられたりしているお客様にお越しいただいております。住宅を購入される方が安心してご検討を進められるよう、スタッフ一同、誠心誠意お手伝いをさせていただきます。
帯山店ともども今後ともansを宜しくお願い申し上げます。
さて、私は23日(日)にansで勉強会を行った後、また全国を回る旅に出ております。
今週は全国各地で工務店さんの集まりがありまして、そちらに参加しています。
月曜が岡山、火曜が大阪、水曜が名古屋で、昨日木曜と本日金曜が東京です。
私はここで「業界動向とこれからの工務店経営」みたいなテーマで少しお話しさせていただいています。
夜の懇親会に至るまで、工務店経営者の皆様といろいろなお話をさせていただいていますが、いつもこういう時に思うのは「住宅業界のみなさんってみんな真面目な方ばかりだなぁ」ということです。
工務店経営者のみなさんは手法は違えども、「お客様に良い家を提供したい」という思いはみな同じです。そのためにこういう勉強会にも頻繁に参加されて自社をよりよくしようと努力しておられます。懇親会でも良い家づくりとお客様の幸せについての熱い議論が尽きません。
それなのに・・・。
いつもお話ししている通り、住宅購入者の約7割は買った後で後悔しているんですね。
なぜでしょうか?
真面目なお客様が真面目な住宅会社と家づくりをする。
どちらも悪くないのに、家づくりがうまくいかない。
こういう状況を改善することもansのテーマです。
例えば、商談を始めてから最終的に家が出来上がるまで、早くても半年以上の時間がかかる長い道のりの間には、何回かコミュニケーションのミスや誤解や混乱などでのトラブルが起きてしまいます。これは人間同士のやりとりですから仕方がないんですね。
こういう時には間に誰か中立的な「通訳」のような人がいるといいんです。
ansは住宅会社さんを紹介して終わりではなく、スタッフが最後まで側に付きます。
原則商談にも同席させていただきます。言った・言わない・聞いてない、ということのないように打ち合わせ記録も取ります。
聞きたくても聞けないこととか不安なことなども「通訳」します。
こんな存在がいるだけで「安心」できることってきっと多いと思います。
真面目な人ばかりのこの業界の「輪」がうまく廻るように、ささやかながらお手伝いができればと思っています。
流通団地店オープン記念!なんと勉強会が・・・
いつもありがとうございます。マラソン後の筋肉痛で歩き方がおかしいansの川瀬です。
さて、いよいよ2月22日(土)AM10:00にansの新店舗「流通団地店」がオープンいたします。
そして、早速新店舗でも「家づくり勉強会」も開催いたします。帯山店よりも少し広いセミナー会場でゆったりと後悔しないための家づくりの基礎知識を学びましょう。もちろん帯山店同様キッズルームも完備していますのでお子様連れの方も安心してお越しください。
今は家づくりに関する情報が氾濫しています。
熊本でもいろんな会社が住宅セミナーなどを開催されていますが、ansは住宅会社ではなく「家づくりのセカンドオピニオン」です。「セカンドオピニオン」とは「中立的な立場から客観的な意見を述べたり助言をする存在のこと」ですね。
お客様が家が出来てしまってから「こんなこと知らなかった~」とか「こんなはずじゃなかった・・・」などと後悔しないように客観的な視点から家づくりのホントのところをお話ししています。もしかしたら住宅会社さんにとってはちょっと耳の痛い話もあるかもしれません。
ほとんどのお客様は家づくりが初めての素人さんです。
モデルハウスや完成見学会などに出向いてもどこをどう見ればいいのか、何が違うのかもわからない人が多いのではないでしょうか。営業担当の方からいろんな話を聞いたとしてもアドバイスなのかセールストークなのかもわからないから不安になる、というのが本当のところではないかと思います。
ansで知識を得ることで家や住宅会社を選ぶ判断基準を持っていただきたいと思っています。家というのは、日用品を買うのとは違います。人生が変わることもある大きな買い物です。お客様が自信を持って「これを選んだ!」と言える状態になってから買っていただきたいと思います。
ansは「お客様が住宅を選べる状態になる」ことを目指して、勉強会や相談面談をやっています。
「家づくりなんてまだまだ先だけど・・」という方でもどうぞお気軽にお越しください。
さて、今週末の勉強会は「資金編」「性能編」「価格編」です。
こんな話を聞くことができます。
↓↓↓
・住宅性能を見極めるためには何を見ればいいの?(性能編)
・性能の違いで健康にも違いが出る?その理由とは?(性能編)
・この住宅会社は高いのか安いのか?坪単価の落とし穴とは?(価格編)
・今買うのがいいのか、もう少し待った方がいいのがどっちがお得?(資金編)
・間違った予算で家を買うと家計が大変に!正しい予算の考え方とは?(資金編)
などなど他では聞けない話がたくさんあります。もちろん知りたいことは何でもお聞きください。
勉強会への参加料は500円(ans会員様は無料)ですが、今回、流通団地店オープン記念としまして、すべて「参加無料」とさせていただきます。
この機会に勉強会にご参加ください。この勉強会のテーマをご家族で家づくりについて話し合うときの参考にしていただけたら嬉しいです。
なお、ansは国土交通省認可事業である九州住宅流通協議会より、「住宅消費者への教育事業」の委託を受けています。安心してお越しください。
素晴らしい大会をありがとうございました
いつもありがとうございます。ansの川瀬です。
昨日、告知しておりました通り、熊本城マラソンに出場いたしました。
私のマラソン出場歴はこれまでハーフを3回、フルは今回で2回目とわずかなものですが、評判通りこの熊本城マラソンはダントツに素晴らしい大会でした。
絶好のマラソン日和。
自らも参加されるという市長さんの開会宣言の後、くまモンに見送られながらスタート。「オール熊本」で大会を盛り上げようという意気込みを感じます。
走り始めてからは沿道の応援にビックリ。いろんな趣向を凝らした応援と途切れることのない声援には本当に感動しました。特に川尻地区の声援スポットと沿道の応援はとび抜けて印象的でした。
25~30kmの熊本港線の長い直線は風もあって一番しんどいところでした。そんな寒い中、アメをサービスしてくれていた子供たちの「がんばれ~」という声援が背中を押してくれました。
35km地点には、今週22日にオープンする我らがansの「流通団地店」があります。ここでのansスタッフの声援とエアーサロンパスで最後の力をもらいました。
(記念撮影をパチリ)
最後の熊本城の坂にはヘロヘロになりましたが、何とか無事に完走できました。
運営は終始スムーズで、スタッフやボランティアの方々の笑顔かつ迅速な 対応には何度も感激しました。ゴール後の荷物返却の時も、遠くから私のゼッケンを見て私が番号を言うまでもなく笑顔で手渡してくれました。
ひそかに目標としていた4時間台はかないませんでしたが、来年(うまく当選できれば)足を鍛えて再チャレンジしたいと思います。
最後に、今回気持ちよく走り終えることが出来て、あらためてスタッフ、ボランティア、交通規制をされた警察や警備の方々、沿道で応援していただいたみなさま、アメをくれた子供たち、そして長時間の交通規制でご不便をお掛けしたにもかかわらず熱心に応援して下さった熊本市の皆様の「心からのおもてなし」に心から感謝申し上げます。
素晴らしい大会をありがとうございました。
2・22 ans2号店「流通団地店オープン!」
いつもありがとうございます。ansの川瀬です。
昨日のお昼に、今年は初めてになりますが、エフエム熊本「パンゲア!」に出演させていただきまして、「ある告知」をしてまいりました。
その告知とは・・・
「私、川瀬が熊本城マラソンに出場します!」
・・・ということではなくて、
「来週2月22日土曜日にansの2号店が熊本市南区にオープンいたします!」ということでした。
ansの2号店名は「流通団地店」と言いまして、場所は熊本市南区江越2丁目、平成大通りとけやき通りの交差点のあたりになります。
明後日開催される「熊本城マラソン」では、ans流通団地店の前を3回走ります。
新店舗「流通団地店」のオープンは22日ですが、マラソンが開催される16日にはもうお店は出来ていますので、当日はansスタッフ全員で、ランナーの皆さんを応援する予定です。
また、応援される方の休憩所としてお店を開放いたします。外は寒いと思いますのでお目当てのランナーが来られるまで店内で暖を取っていただいたり、トイレなども使っていただいて構いません。 どうぞお気軽にお入りいただいて、ansの新店舗をご活用いただければと思います。
1号店である「帯山店」には広く熊本県内よりお越しいただいておりますが、「アクセスに時間がかかる」とか「近かったらもっと勉強会に行きやすいのに」といったお声をいただいておりましたので、このたび熊本の南エリアに「流通団地店」をオープンすることとなりました。
流通団地店でも、帯山店と同じく「後悔しない家づくりのための勉強会」を毎週末に開催してまいります。
流通団地店オープン記念としまして、ひとりでも多くの方にansの勉強会を体験していただきたいので、お披露目をかねまして、2月22日(土)、23日(日)の勉強会の参加費を通常500円のところ「無料」とさせていただきます。
・2月22日(土)13時30分~15時「賢い資金計画勉強会(初級編)」
・2月23日(日)10時~11時30分「賢い住宅会社選びのポイント:価格編」
・2月23日(日)13時30分~15時「賢い住宅会社選びのポイント:性能編」
是非この機会にお気軽にご参加ください。(→詳しくはこちらから)
「勉強会には行きたいけどどうしても休みがあわない」とか、「聞きたいタイミングで聞きたいテーマじゃない」という方などもいらっしゃいます。そのような方に向けまして、個別相談を帯山店、流通団地店のどちらの店舗でも、いつでも受付しています。仕事終わりの平日の夕方でもOKです。住宅会社の選び方、ファイナンシャルプランニング、土地探し、その他わからないこと、確認したいこと、何でもご相談に来て下さい。
そろそろ家を建てようかなとお考えの皆さんだけでなく、まだまだ先だけどいつかは建てたいな、という皆さんもお気軽にお越しいただければと思います。
ansは住宅選びの「セカンドオピニオン」ですので、売り込みなどは一切ありません。中立的な立場でアドバイスをさせていただきます。
これからもどうぞansをよろしくお願いします。
あ、熊本城マラソンも頑張って走ります!
ansのやりたいこと
いつもありがとうございます。ansの川瀬です。
私たちansの理念は「お客様がより安心して、後悔することなく、家を建てることができる環境を作りたい」というものです。
逆に言えば、今の日本の住宅購入環境は、「買いやすくない」と考えているということです。
みなさん、「どこの住宅会社で、どんな家を、どれくらいの予算で建てればいいのか」ということがよくわからずに、不安を持ちながら家を建てています。 その結果として、多くの方が建てた後に「こうすればよかった」「こんなことは聞いていなかった」などと後悔されているのです。
ansの役割をご理解いただくために、ちょっとだけ小難しい話をします。
マーケティングの世界で『購買意思決定プロセス』というものがあります。消費者がある製品やサービスの購入を意思決定するまでの間には、いくつかの段階がある、というものです。
この「購買意思決定プロセス」とは、
「問題認知」→「情報探索」→「代替品評価」→「購買決定」・・・となります。
住宅で言うとこんなプロセスです。
1)「問題認知」・・・「子供も大きくなってきて今の賃貸では狭いな~。」「家賃ももったいないし。」「若いうちに家を買っておかないと老後に苦労するとかきいたな」といったような今の住まいに問題を感じて「家を買おうかな」と感じる時ですね。
2)「情報探索」・・・「さて、家ってどうやって買うのかな。」「マンションかな戸建かな?」「新築かな中古かな?」という疑問を解決するための情報探索が行われます。住宅情報雑誌を買ったり、ネットで調べたり、親や友人に聞いたりする段階です。もう一歩すすむと、住宅展示場やモデルルーム、不動産仲介会社などに出向いて担当者から話を聞いたりして情報を入手します。
3)「代替品評価」・・・「では、どの住宅会社にしようかな?」と、情報探索によって得られた情報をもとに、具体的に住宅会社の評価し、比較して、選択を行います。
4)「購買決定」・・・そして、「じゃあここに決めます」と、代替品評価の結果にもとづいて購買決定を行います。
・・・ということなんですが、今の日本の住宅購入環境では、「問題認知」をした後で「よし、家を建てよう!」となった時、そのあとの各プロセスで相当苦労すると思います。
まず、「情報探索」が大変です。
おそらく、雑誌やネットを見ても、世の中に溢れかえっている住宅に関する情報を判断して整理していくことはとても難しいでしょう。建築、法律、金融、税金など見知らぬ分野の専門用語がいっぱい出てきます。「よくわからないから直接聞いてみよう」と思っても、住宅会社や不動産仲介会社は各地に点在していて2~3社も回ったら一日は終わってしまいます。おそらくこの段階で「家づくりって大変だな・・・」と感じられると思います。
さらに次の「代替品評価」がまた難しい。
ここが私たちが日本の住宅購入環境で一番問題だと感じているところです。
得られた情報を比較して検討しようにも、まず比較する基準がわからないはずです。住宅会社ごとに家のコンセプト、デザイン、部材や性能など、本当は全然違うのですが、おそらく多くの方はその違いを本質的には評価できません。
どこに行っても、「この部材は最高ですよ」「家の作り方はこの工法が一番です」と言われますからね。
「新築なんだからどこの家も頑丈で、暖かい省エネ住宅なんだと思っていました」というお客様もいらっしゃいました。
最後に、結果として、「何となくのイメージ」と「価格が安いから」といったことだけで決めてしまいがちなんです。
ansでは、まずお客様に 「情報」を整理するための「基礎知識」をご提供します。最低限これだけ知っておくだけで、性能や価格、土地選びやローンのことなど色んなことが判断できるようになる知識を勉強会や個別相談会で学んでいただきます。
そして、お客様の適正予算と趣味思考に基づいて、何百とある住宅会社の中からふさわしい住宅会社さんをピックアップして、その住宅会社さんの情報をお伝えします。お客様が住宅会社を回らなくてもansで同時に複数社の比較検討ができます。(ラクでしょ?)
よく勘違いされるのですが、ansは住宅会社さんをお勧めはしません。
ansが行うのは「情報公開」です。判断するのは私たちではなく、お客様です。
ansで勉強して、個別相談を受けていただたお客様なら、自分なりの判断基準ができているはずですから。
住宅会社さんを決めたあとも、土地選定、プラン打ち合わせ、仕様決め、見積もり、契約と打ち合わせは続きます。途中でコミュニケーションがうまくいかず厳しい状況になることも、しばしばあります。そんな時には、第三者的立場で打ち合わせに同席しているansスタッフが頑張って調整します。
間に一人いるだけで意思疎通がうまくいくことは結構多いのです。
このようにしてお客様が「より安心して、後悔することなく、家を建てることができる環境を作りたい」と思い、日々スタッフ一同頑張っております。
「情報探索」に疲れたり、「代替品評価」の段階でどう選んでいいかわからない、となったらどうぞお気軽にansにお越しください。
スタッフ一同、お待ちしています。
熊本城マラソンに・・・
いつもありがとうございます。ansの川瀬です。
早いものでもう2014年も1か月が過ぎようとしています。
早いですね・・・。
私、かなり焦ってきております。
なぜかと言いますと、来る2月16日(日)の「熊本城マラソン」が人の気も知らずに近づいてきているからです。
半年くらい前に、飲んでる時の勢いで「みんなでエントリーしよう!」ということになりまして、そうしたらラッキーにも当選しました。
気楽に走ろう、ダメなら途中でやめてもいいし・・・くらい気軽に考えていたのですが、周りから「ansを名誉をかけて走るんだぞ!」というようなプレッシャーが次第にかかるようになり、噂では「ans」のロゴ入りのシャツの制作なども進んでいて、それを着なければならないとか・・・。
私はスポーツは好きなのでジョギング程度に走ってはいますが、あくまでお気楽ランナーです。
目標は「5時間台で完走!」(できたらいいな)くらいのレベルです。
「ans」のロゴを背負って走るのなら、なんとか最後まで、リタイヤせずに、笑顔でゴールしたいものです。
そのために今、できるだけ隙を見つけてトレーニングしよう、という気持ちだけはとても強いのですが・・・、そうは言っても朝は寒いし、夜は遅くまで飲むし、でなかなか走れないんですよね。
「当日は楽しんで走りたい」とは思っていますが、きっとフラフラのへろへろになるんだろうな~とネガティブ思考になっています。
もし、無様なことになっていたとしても、どうか暖かいまなざしでそっと見守っていていただければと・・・。
早い月日の流れに気ばかり焦っている川瀬でした。
クルマと家の省エネ化について
いつもありがとうございます。ansの川瀬です。
今日はまずクルマの話です。
日本自動車工業会によると、2012年度の新車の平均燃費は21.6km/Lだったそうです。
2008年度が16.8Km/Lでしたので、4年間で約5kmも伸びたことになりますね。
政府目標は2015年度に17.5 Km/Lでしたから、はるかに超える水準で、前倒しで達成してしまいました。
ここ数年の間で日本のクルマはエコ化が急速に進みました。
昨年、2013年度の新車販売トップ10は、トップのアクア、2位のプリウス(どちらもトヨタ)をはじめとして、すべてハイブリッドカーやエコカーで占められました。
クルマのエコ化の流れを振り返ってみたいと思います。
元々、クルマのエコ化は「排ガス規制」や「CO2削減」など環境問題に端を発しています。
それが一気に拍車がかかったのが2008年でした。
2008年にアメリカの金融緩和を背景にして投機マネーが市場を席巻し、原油価格も高騰しました。2008年夏には1バレル140ドルを超えました。当時は連日、ガソリン代の値上がりがニュースになっていましたね。(政権交代する前の民主党の議員達が「ガソリン、値上げハンターイ!」とかやっていましたね。)
結局、バブルが崩壊するように原油の高騰は一気に収まるんですが、私たちの心の中には「ガソリン代が値上がりすると家計が大変になる・・・」ということが刻まれました。
クルマの省エネが「環境問題」から「家計問題」として実感された瞬間だったと思います。
原油が簡単に値上がりする時代に「がんがんガソリンを食うようなクルマに乗っている場合じゃない」という意識になったのです。
続く2009年にリーマンショックが起きて、景気はどん底になります。景気回復のため、政府はエコカーへの減税や補助金の名目で自動車産業を支えました。これで一気にエコカーへの買い替えが進んだわけですね。
2009年にはついに「プリウス」が販売台数トップになります。(以降プリウスは2012年までずっと首位の座を守ります)
エコが「環境問題」から「家計問題」としてみんなの意識に刻み込まれた瞬間に自動車のエコ化が加速して、それから5年で業界のエコ化が完了したと言えます。
さて今、住宅にも全く同じ流れが来ています。
きっかけは原発問題に端を発した「電気代の値上がり」です。さらに昨年、円高から円安になったことで原油やLNGの輸送費や輸入決済額も上昇しました。電気代だけでなくこの冬は灯油代も値上がりしています。
いつもよりちょっと寒いこの冬、電気代と灯油代の値上がりは家計を直撃しています。
住宅の省エネ化も「環境問題」から「家計問題」になっています。
「これから電気代などが値上がりするかもわからない時代に光熱費ががんがんかかるような家に住んでいる場合じゃない」という意識に皆さんがなり始めているんじゃないかと思います。
そんな時に、消費増税があり、家の新築、建替えが増えています。
政府は「2020年に省エネ住宅を義務化する」ことを明らかにしています。2020年にはすべての新築住宅が、国が定める断熱性能などの省エネ基準を達成しなければなりません。
中古住宅についても断熱リフォームを推進していく方針が決まっています。
ただ統計では、現在はまだ新築一戸建で国が定める省エネ基準を満たしているのは全体の4割弱程度なんです。
ここが自動車業界と大きく違うところです。
クルマと同じように、2020年を待たずに日本のすべての新築住宅が断熱性能のいい家になって、皆が省エネ住宅で快適に暮らせるようになるといいですね。
日本の住宅の「エコ化」は、これからますます進んでいくと思います。
2014年が、その「エコ住宅普及元年」になることを願っています。
2014年の住宅購入環境は?
いつもありがとうございます。ansの川瀬です。
みなさま、もうすっかり正月気分も抜けて順調に2014年をスタートされたことと存じます。
全国の工務店経営者の方々とお話しをしておりますと、この年明けからさっそくお客様が動き始めているという声が多いようです。8%増税の駆け込み契約が一段落した昨年秋以降、注文住宅市場は比較的静かだったのですが、またお客様が住宅イベントや現場見学会に来られるようになっているようです。
ansにも12日~14日に行った勉強会だけでなく、平日の個別相談にも住宅購入をお考えのお客様が続々とお越しになられています。
年末年始に家族が集まった時などに「家のこと」についていろいろなお話しがあったんでしょうね。
何より「住宅を買うのであれば2014年は最後の買い時タイミングなのではないか」というお考えの方が多いのではないかなと思います。
住宅購入タイミングはみなさんのライフプランもありますので、それぞれの家庭ごとにじっくり考えべきだと思いますが、もし、もう買うことが決まっていてタイミングを見極めておられるのであれば、最適な買い時タイミングは「今年の秋まで」というのがひとつの目安時期になるのではないかな、と勝手に考えております。
今年の4月に「5%→8%」に増税されますが、「3%くらいならまだ大丈夫。住宅ローン減税もあるし。」というお客様が多くいらっしゃいました。そういう方でも「さすがに10%になる前には…」とおっしゃいます。
今年の景気動向を「消費税」を軸に予想してみたいと思います。
政府は、2015年10月に消費税をもう一段階「8%→10%」へ増税をするかどうかを、「2014年度の7月~9月の経済状況を見て判断する」と言っています。
4月に8%に増税されると一旦消費は落ち込むと思いますが、それが7月以降にどれだけ回復しているかを次の10%への増税の見極め材料とするわけですね。
ただ、日本の財政を見通したときに「消費増税はしなければならない」というのが世の中のムードになりつつあります。政府(特に財務省)としても増税は規定路線ですからなんとしても景気回復スピードを落とすわけにいきません。
意地でも2014年7月~9月のGDPは増やしたいと考えています。
だから2014年度の歳出予算は過去最大の95兆8800億円という大盤振る舞いです。
もしかしたら、4月~6月にはもう一段の金融緩和があるかもしれません。
(←つまり金利は上がらない)
6月には「新成長戦略」もまた出される予定です。
つまり、秋ごろまで好景気ムードが醸成されるわけです。
ちょっとインフレになるかもしれません。
好景気でインフレですから、材料費や燃料費、人件費などは上がっていきます。
つまり住宅の原価は徐々に上がっていくでしょう。
でも金融緩和のおかげで金利はそれほど上がらないでしょう。住宅ローンは組みやすいと思います。
それが今年の秋ごろに「2015年10月に消費税を10%にします」と決まったら、その時から2015年3月まではまた住宅駆け込みが加速するかもしれません。
そのタイミングでは住宅価格はさらに上がるかもしれません。
そういったことを感じている方が多いから年明けからまた住宅市場にお客様が戻ってきているのではないかなと思います。
少しでも安く買いたい方は「消費増税の決定前(おそらく今年の10月)」までに決めておきたいものですね。
(以上、まったく勝手な私見でございます。あくまで参考程度に。)
新しい投稿ページへ古い投稿ページへ