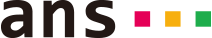未分類カテゴリー記事の一覧です
米のパリ協定離脱はさすがに「ない」
いつもありがとうございます。ansの川瀬です。
あまりに爽やかな5月があっという間に過ぎ去って6月になりました。5月の月間降雨量は過去最低水準だったそうです。
6月といえば梅雨。ジメジメして嫌な季節ですが、雨が降らないと農作物が育ちませんので空梅雨にならずにしっかりと雨は降ってもらわねばいけませんね。
自然環境と言えば…、
トランブ大統領がなんと、地球温暖化対策の国際合意である「パリ協定」からの離脱を表明しましたね。
私は別にトランプ大統領の支持派でもなんでもありませんが、これまでは割とトランプ大統領の政策を好意的に見ていました。金融規制緩和とか法人税減税、大規模な財政出動などトランプ氏が選挙の時に経済面で掲げていた政策は景気を良い方向に刺激するだろうし、それは日本にとっても悪いことではないと思っていたからです。
しかし、今回のパリ協定離脱はさすがに「ない」ですね。
トランプ大統領は、欧州主導の枠組みにはまりたくなかったのか、自国の石炭業界や鉄鋼業界のウケを狙ったのかわかりませんが、これはアメリカが良い方向に向かう決断だとは到底思えません。
アメリカ国内でもパリ協定離脱賛成派は1割強程度しかいないとか…。GEやマイクロソフトなど産業界も即座に反対の姿勢を示しました。
「いや、地球はむしろ寒冷化している」とかいう説もありますし、確かに地球温暖化に関しては様々な異論はあります。温暖化を利益誘導に使っている国や組織もあるのかもしれません。しかし、環境意識の高まりはすでに世界的な潮流になっています。この流れはもう止められないでしょう。産業界も一般消費者も意識は環境保護に向かっています。日本でも自動車も住宅も随分エコ化しましたよね。この先もっと環境技術は様々な分野で進歩していくと思います。
トランプさんがなんと言おうが世界的なこの流れはもう後戻りはしないでしょう。明らかに京都議定書の頃(2001年)とは状況が違います。
再生可能エネルギーの開発にしても省CO2関連技術の開発にしても環境分野に向けた取り組みをしていない、なんて企業はもういないでしょう。環境分野の技術革新が企業の成功要因のひとつに確実になっていくことを考えると、この先アメリカの企業は国際的に競争力を失っていくかもしれませんね。
フランスのマクロン大統領がアメリカの科学者に向けて「フランスで一緒に働こう」と皮肉っぽい声明を発表していましたが、冗談ではなく今後アメリカから環境技術分野の頭脳流出が起きるかもしれませんね。
しかしトランプ大統領、なにかと滅茶苦茶になってきていますが、大丈夫でしょうかね?(私が心配してもどうもなりませんが)
日本は今後も変わらず環境技術を磨く国でありたいものです。
スーツも家もカスタマイズの時代
いつもありがとうございます。ansの川瀬です。
5月に入って完全に季節が変わりましたね。もう日差しは夏です。
今日の東京の最高気温の予想はなんと28度とのこと(+_+) みなさま、どうぞ体調を崩されませんようにお気を付けください。
さて、変わったと言えば先日こんな記事がありました。
↓↓↓
<スーツ 体にぴったり パターンオーダー進化版> (2017年5月6日付 読売新聞)
『簡易なオーダーメイドで紳士物のスーツをあつらえる「パターンオーダー」が人気だ。これまでより細かいサイズ調整が可能でデザインにも優れた「進化版」のパターンオーダーが増えているためだ。体にあったスーツを試してみてはいかがだろうか。』
スーツには既製品のいわゆる「吊るし」と「オーダー」の2種類がありますね。そして、オーダーにはさらに3つの種類がありまして、採寸して手作業で作る「フルオーダー」、仮縫いを省いてコストを抑えた「イージーオーダー」、そしてベースのスーツを基に着丈や袖丈などの長さを調整して作る「パターンオーダー」があります。この記事によると最近はパターンオーダーが進化して、胴回りとか肩幅、すそ幅なども調節できる進化版が現れてきていて人気があるとのことです。
例えば、かつては「吊るし」(=形が決まっている既製品)しかやっていなかった「洋服の青山」とか「AOKI」とか「紳士服のコナカ」などのスーツ量販店でも新しいパターンオーダーの新ブランドを続々立ち上げていますね。
私も最近は、もっぱらパターンオーダーでスーツを作っています。体格に合わせてくれるだけではなくて、生地やポケットの形、ボタンとか裏地まで選べるのも楽しくていいですよね。「オーダー」というと高いイメージがありますが、このパターンオーダーなら大体3万円くらいから出来ますので、もはや吊るしと変わらない価格帯です。それは人気も出るでしょう。
紳士服市場は、団塊世代の退職やクールビスの影響などで全体的にはずっと縮小傾向にあるそうですが、このオーダーメイド市場だけは逆に伸びているらしいです。
ニーズがいっぱいあって市場が伸びている時には大量生産をしてコストパフォーマンスを上げるのがいいのでしょうが、市場が小さくなってきたときには、大量生産をすると在庫ロスが出るリスクがありますので、むしろ多様化したニーズに合わせてカスタマイズする方が利益が出る、というのはよくある話ですね。
実は、家もそうですよね。
みんなが家を買う経済成長期には、建売住宅とかマンションとか、いわば「既製品」のような住宅でもどんどん売れます。人口が増えている東京など大都市圏などでは今もそうですよね。
しかし、かつてほど家が売れなくなっている地方都市などに行きますと、その地域の住宅各社は様々な工夫を凝らした家を提供し始めています。完全な注文住宅はいわば「フルオーダー」ですから、ちょっと予算的に手が出ないという方でも、ベースのプランからいろいろと変更ができる「パターンオーダー」のような家であれば手頃な価格帯で手に入れることができます。
「パターンオーダー」や「イージーオーダー」のような家をコストを抑えて提供している住宅会社さんも増えています。そういう家を建てたお客様も「私たちの暮らしに合わせて建ててくれたのでこれで十分満足」と喜ばれています。
スーツも家も時代に合わせて変わっていきますね。
そういう「家の作り方の違い」というようなこともansの勉強会の「価格編」の中でお話ししています。ansの勉強会では家を建てる前には絶対に知っておいた方がいいことが満載ですよ。お待ちしておりますね。
(ansの勉強会のスケジュール、お申込みは こちら から)
どうでもいい現金の話
いつもありがとうございます。ansの川瀬です。
先日、新聞に「タンス預金が増えている」という記事がありました。
↓↓↓
<タンス預金が止まらない 3年で3割増、43兆円 富裕層、現金志向強める>
(2017年4月3日付 日本経済新聞)
「タンス預金」、銀行に預けずに現金で保有されているお金のことですが、それがなんと43兆円もあるそうです。今発行されている紙幣はおよそ99兆円あるそうですが、そのうち預金や決済などに使われている分、すなわち金融市場に出ている分は56兆円しかない、つまり43兆円は家計に眠っているらしいのです。
99兆円のうち43兆円も家のタンスか床下か金庫か知りませんが、眠っている。しかもこの3年で3割も増えているとのこと。
このキャッシュレス時代に、いったいなぜ、最近急にタンス預金が増えているんでしょう?
同記事によると、要因のひとつは「低金利」だそうです。
確かに銀行に預けていても、時代はゼロ金利です。預金利息はほぼ付きません。引き出したり、振替などをするたびに手数料が取られることを考えますとこれはもう実質的に「マイナス金利」です。「銀行に預けても損をする。だから手元に置いておく」という考えはわからないでもありません。
しかし、タンス預金には盗難とか火事などの災害で現金を失ってしまうリスクもありますよね。多くの人は、預金は実質的にマイナス金利状態であってもリスクを避けるための保管コストと割り切って考えていると思います。
そんなリスクを負ってまでもタンス預金が増えているのはマイナス金利の影響だけではないですね。
間違いなく一番の要因は「マイナンバー」でしょう。
マイナンバーですべての銀行口座の動きがわかるようになりました。私たち庶民には関係ない話ですが、多額の納税をしているような富裕層の皆さんはお金のやりとりを税務署に捕捉されることを嫌います。脱税とか極端な話じゃなくても、そもそも色々詮索されること自体が嫌なのです。
私、社会人の最初の10年ほどは銀行員をやっておりましたが、お客様の要望に応じてよく多額の現金を運んでいました。
今でこそ厳しくなりましたが、名義がよくわからない口座があったりすることもありましたね。今は本人確認も相当厳しくなり、そんな名義があやふやな怪しい口座は作るができなくなりました。一回での取引金額にも制限があります。お金の移動そのものへの監視が厳しくなっているのは事実です。だから、余計にお金のやりとりの記録を残したくないという人が一定の現金を手元に置いているだと思います。
だから今、大きな金庫が売れているのだそうです。しかし金庫は相当重いですから、万が一の時に持って走るようなことは出来ませんね。
そもそも紙幣も億単位になってくると結構重いのです。
銀行員になった新人の男性が一番最初にやることが多い仕事が、窓口の後方でお金を整理する仕事です。「資金係」と呼ばれ、来る日も来る日をお金をまとめて束にして、金庫に運んだり、現金輸送車に載せたりします。
これがかなりの力仕事なのです。例えば、一人で抱えて運ぶことが可能なのは大体1億円までです。1億円だと重さは約10Kg。1千万円の束の高さがおよそ10cmなので1億円ともなるとうまくまとめないと片手では持てません。2億円ともなってくるともう台車が必要です。
先日、福岡で3億8000万円もの現金が盗まれたという事件がありましたが、まずそのニュースを聞いて感じたのは「よく運べたな」ということです。3億8000万円というと重さで約38Kg。キャリーバックに入れていたということですが、相当重くてうまくコロコロも引けないと思います。
運ぶ方も大変なら強奪する方も大変です。やはり複数人の犯行ということでした。物騒な話なので早く解決してもらいたいものですね。
現金にはリスクがある、ということと、現金は重い、という、まあどうでもいい話でした。
熊本地震から一年
いつもありがとうございます。ansの川瀬です。
宣言通り、昨日の朝、ちゃんと早起きして皇居周りを走りましたよ。
(証拠写真)
↓↓↓
千鳥ヶ淵の桜はまだ十分咲いていて、ちょっとひんやりした朝の空気がとても清々しかったです。
(ただ、久しぶりに走ったので後半はバテバテ…。一日経ったいま筋肉痛です。)
さて、今日で熊本地震から一年ですね。
一年前の4月14日の夜と16日に相次いで震度6強の地震が熊本を襲いました。あの地震で人生が変わってしまった人たちが熊本にはたくさんいらっしゃいます。
報道によると、関連死も含めて225名の方々が亡くなられました。損壊した住宅はおよそ19万棟。今も4万7千人以上の方々が仮設住宅に暮らしていらっしゃいます。
家が損壊してしまい、建て替えや転居などをせざるを得なくなったご家族が数多くansにもお越しになられました。お話しを伺うととても大変な状況にある方ばかり…。
それでもほとんどの皆さんは、「前を向いていくしかないからね」と明るい表情で話されます。
まだまだ復興は道半ばです。私たちが出来ることなど知れていますが少しでもお力になれるように、これからも力を尽くしていこうと思っています。
熊本とともに。
春本番
いつもありがとうございます。ansの川瀬です。
春が来ましたね。東京でも熊本でも桜が満開です。
桜を見るとなぜか心が躍りますね。人生で新しいことが始まることが多いのが4月で、桜の季節には新しいことに向けてワクワクしてきた記憶が心躍らせるのでしょうか。入学、進級、クラス替え、就職など、皆4月ですもんね。街には真新しい制服に身を包んだ新入生や、着慣れないスーツを着た新入社員の人たちが溢れています。
初々しいなぁ。…と眺めているわけです。
私にも新入生だった時や新入社員だった時がありました。(遠い昔ですが)
初々しかった(だろう)と思います。
今は初々しさのかけらもありませんが、それでも春を迎えると気持ちがちょっとだけ上がりますね。何か新しいことを始めたくなります。
「よし、それならこれから毎日、ちょっと早起きしようか。」
いつもだいたい朝は7時頃起きるのですが、1時間早い6時に起きることにしよう、と。暖かくなったし、桜も咲いていることだし。
そういうことで、今週の出張から朝、走ることにしました。
実は、風邪で倒れた2月以来走っていません。よし、また走ろう!と思って、シューズとウェアをキャリーバッグに入れて東京出張に出ました。せっかくだから桜を見ながら走りたいので、火曜に目黒川沿いを、木曜に皇居周りを走る予定にしました。
しかし、今日(火曜)、朝起きると外は冷たい雨。雨の中でも走る人はもちろんいますが、私はそこまで気合が入っていません。6時にいったん起きましたが、外を見て、すぐもう一度ベッドに潜り込みました。
結局、今朝も起きたのは7時でした…。
出鼻をくじかれましたね。
明日の朝は早朝移動なので、明後日。絶対6時に起きて走ります。晴れたらですけど。
さて、新しいことと言えば、「そろそろ家づくりを始めようかな」と考えている方もいらっしゃるでしょう。そういう皆さまは「まずans!」ですね。
今週16日日曜は、私、ans流通団地店にて午前は資金勉強会、午後は土地勉強会の講師をいたします。皆様のご参加をお待ちしております。
ちゃんと早起きして、しっかり講師を務めますので。
コロコロの置き方を女子高生に学ぶ
いつもありがとうございます。ansの川瀬です。
今日は「老いては子に従え」的な話です。
移動が多い私たちにとって相棒のような存在なのがキャリーバッグ(通称コロコロ)です。私はもう何台も「壊れては買い替え」を繰り返してきました。私のこだわりは車輪が四輪ではなく二輪であること。しかも出来るだけ車輪は大きめで頑丈なやつです。これを後ろ手でコロコロと引いて歩くのが好きなのです。
(二輪のイメージはこんな感じです)
四輪は、車輪が小さくてよく壊れてしまうことが多いし、何より電車の中などで置いておくと勝手にすーっと動いてしまうのが決定的にイヤなところです。その点、二輪は置いておいても言いつけをよく守る実直な兵士のようにじっとその場に立っています。
しかしながら、最近のキャリーバッグ事情は完全に四輪全盛時代。どこの売り場も四輪だらけです。二輪は探すのが大変になってきていました。
そんな中、2か月ほど前の博多への出張中に、愛用していた二輪コロコロが壊れてしまい使えなくなってしまいました。まだあと数日そのまま出張が続くので仕方なくその日の仕事の合間をぬって博多のデパートでキャリーバッグを買いました。四輪の割と大型のやつです。それしか置いてなかったし、もう時間もないので背に腹は代えられません。「音のしないスムーズな車輪の動きが自慢です」と店員さんは勧めてくれたのですが、「私はそれがイヤなんですけど」とも言えずに初めて四輪を購入しました。
(これと似たタイプのやつです)
↓↓↓
初めての四輪。
持って歩くときは大型の割に確かに静かだしスムーズです。しかし、やはりちょっと手を離して置いておいたりするとかなり勝手に動く。電車の中などは絶対取っ手をしっかり握っておかないといけないし、駅のホームは傾斜があるので、置いておくとすーっと動いてホームから落ちそうになります。ウロチョロ動く子供のようなものでとても手がかかります。
そんな手のかかる状態にも慣れてきた昨日、新潟から上越新幹線に乗りました。そこで問題が発生しました。
上越新幹線は2階建てなので天井が低くなっています。いつも乗っている東海道新幹線だとこの大型四輪コロコロでも上の棚に問題なく置けるのですが、天井が低くてスペースの狭い上越新幹線の棚にはこのコロコロが大きすぎて入らないのです。
う~ん、どうしよう。
自分の足元に置くと足を置くスペースがなくなるし、今から東京までの2時間ずっと手で押さえておくのも大変だし・・・。
歩いてきた車掌さんに「このキャリーが棚に入らない。足元に置くと狭くなる。どうしたらよいか。」と聞くと、「後ろに置いていいですよ。」と後ろを指し示します。私が座っていたのが車両の進行方向最後部の通路側でしたので、シートの後ろにちょっとしたスペースがあって、そこによく荷物が置かれているのはさすがに知っています。
「いや勝手に動くのですが・・・」と言っても聞こえなかったのか、意味がわからなかったのか、車掌さんはニッコリ笑って行ってしまいました。仕方がないので私の前に置いて動かないようにキャリーを足の間に挟んでいました。
新潟を出て次の燕三条駅で女子高生らしき子が乗ってきました。受験か何かでしょうか。見ると大きな四輪のコロコロを持っています。
私の横の窓側の席だったようで、「すみません」と言いながら奥の窓側の席に手に持った小さなカバンを置きます。
「お嬢さん、お気の毒だがその大きなヤツは上の棚には入りませんし、後ろのスペースに置くと動き回りますよ・・・」と心の中で思っていると、
「後ろ、よろしいですか?」と。
大きなキャリーバッグを後ろのスペースに置こうとします。
「えっ」と思う間もなく、その女子高生は、スッとキャリーバッグを横に倒して、キャリーバッグの側面の下にして置きました。
(こういう感じです)
↓↓↓
むむむっ。
確かに!
その手があったか!
というか、そりゃそうだよな。
女子高生のコロコロは新幹線の揺れにも静かに寝ているかのように微動だにしません。
女子高生を奥の席に通した後、それまで私の足元にあった私の大型四輪コロコロも横にして、女子高生のコロコロの隣にそっと寝かせました。
(は、恥ずかしい・・・)と思いながら。
新幹線出張を繰り返す仕事について20ン年。恐らく初めてキャリーバッグを持って東京へ行ったのであろう(想像)女子高生に四輪コロコロの正しい置き方を教えてもらいました。
年齢を重ねるうちにモノの見方が硬直しているのではないか、と大いに反省した出来事でした。
あれから6年
いつもありがとうございます。ansの川瀬です。
今日は珍しく土曜日に勉強会を開催します。私は帯山店にて午前は「住宅の価格勉強会」、午後は「資金勉強会」です。多くの皆さまに参加のご予約をいただいていますので楽しみです。
さて、今日は3月11日。あの東日本大震災から丸6年経ちましたね。
あの日のあの時間、私は東京駅に向かう新幹線の中にいました。品川駅を出て東京駅に向かう時、田町駅あたりで新幹線がすーっと止まり、「大きな地震を感知しましたので緊急停車しました。」とアナウンスが流れました。その直後に、ガガガーっと来ました。すごい揺れでシートにしがみつきました。窓からみえる芝浦の高層ビル群が大きく左右に揺れていて「これは大変な地震だ」と身構えた記憶があります。揺れが収まった後も新幹線はかなり長時間復旧せず、結局そのまま約8時間、停車した新幹線の中で過ごしました。
その間、ケータイのワンセグでずっとニュースを観ていましたがこの世界で起きているとは思えない映像に言葉を失っていました。
深夜近くになってようやく東京駅に着いたのですが、東京駅は帰宅できない人たちでごったがえしていましたね。私もそこで一夜を明かしました。
あれから6年ですか。時間の経過は速いですが、東北の復興はまだまだ続いていますね。
昨年は熊本でも震災がありました。熊本の皆さんも復興に向けて頑張っておられます。私の出来ることなど知れていますが、自分の持ち場で一生懸命働こうと思います。
まずは間もなく始まる勉強会からですね。熊本で新たに住宅建築を検討しておられる皆さまに参考になるような話が出来るように頑張ります!
御礼!熊本城マラソン、でも私は…。
いつもありがとうございます。ansの川瀬です。
熊本城マラソンから一週間経ちましたね。ランナーの皆さんの筋肉痛も取れてきた頃だと思います。
私ですか、それが・・・、大変申し上げにくいのですが、
なんと欠場してしまいました。
実は風邪を引いてしまいまして、応援にも行けず自宅で寝ておりました…。
本当に面目次第もございません。
熊本城マラソンの3~4日前くらいでしたか、出張先で朝ランしておりましたら10㎞くらいのところで猛烈に眠くなってフラフラになってしまいました。確かに気温も2~3度で寒い朝だったのですが、これまでそんな朝でもそんな状態になったことは一度もありません。眠くてふわふわして、そしてとにかく寒くてガタガタ震えながら、何とかホテルに戻りました。フロントで体温計を借りて測りましたらやはり大いに発熱しておりました。
これはまずいな~と思いつつ、翌日にかかりつけ医のところ行きましたら「風邪ですな」と。「マラソンなどとんでもない。最低でも日曜までは自宅療養!」ということになりまして、涙をのんで欠場した次第です。
「病は気から」といいますが、決してマラソンが嫌だったわけではありません。何だかんだ言っても走る気は満々で追い込みで走ってもいたのです。それがこんなことになるとは…、せっかく3年ぶりに抽選に当たったのに残念でなりません。
ansからはいつもの塩崎のほかに3人が出走しまして、皆見事に完走しました。
彼らが着ていたansのウエアを見て、「アンズさん、頑張れ~」というような声援を至る所でいただいたそうで、出走ランナー一同感動しておりました。
いつもありがとうございます。来年こそは! 頑張ります!(体調も整えて)
熊本城マラソン、出ます。
いつもありがとうございます。ansの川瀬です。
今日はans流通団地店で勉強会講師の日でした。午前中は「建物性能編」、午後は「建物価格編」というカリキュラムで、時間いっぱいまで心を込めてお話しさせていただきました。最近、勉強会に参加される方が増えているようです。今日も満席。皆さんとても熱心にメモを取りながらお聞きいただきました。これから家を建てようと考えている皆さまの住宅選びの参考に少しでもなれば幸いに存じます。
ということで、久しぶりに熊本に来ました。昨日まで東京に居まして、ずっととても寒かったのですが、熊本も寒いですね。早朝に熊本空港に着いた時はなんと気温0度でしたからね。
こんなに寒いにも関わらず、空港からansのお店までの移動中に走っている人を何人も見かけました。
そうですね。いよいよ熊本城マラソンが来週日曜日に開催されますからね。恐らくランナーの皆さんが最後の仕上げにかかっているのだと思います。皆さん、頑張ってくださいね。
…などと他人事のように言っていますが、実は私も今年は出場する予定です。
熊本城マラソンは3年ぶりです。
マラソンコースの途中(5キロと35キロ地点)にansの流通団地店がありますので、例年、沿道で応援する皆さんにお店を開放しまして、暖かいお飲み物などとともにテレビ中継を見ていただいたりしています。
ここ2年は抽選で漏れたのでansで応援に回っていたのですが、ついに当選してしまいました。
心配なのは、ほぼ間違いなく練習不足であること。マラソンを真面目にやっている人は月間200キロ走る人もいたりしますが、私はだいたい月に50キロも走りません。
「走った距離はウソつかない」という言葉があります。トレーニングした分だけ記録は伸びる、ということかと思いますが、そうだとすると私の熊本城マラソンが悲惨な結果になることは今からもう明らか、ということになります…。
なぜトレーニングしなかったのか、ということに対して言い訳すると何時間でも語りますが恐らくミジメな気持ちになるので、もう語りません。潔く、黙って走って、ボロボロになろうと思っています。
目標は「制限時間内に完走」です。
ansからは塩崎も出走しますが、噂では(仕事もそこそこに)かなり走り込んでいて、「今年はタイムにこだわる」とか言っているらしいです。彼の挑発にはくれぐれも乗らないようにします。
当日はans流通団地店にて応援を賜りますよう宜しくお願いいたします。
ちなみにマラソンコースから大きく離れている帯山店ではいつも通り勉強会をやっております。ぜひそちらにもお越しくださいませ。
(は~、憂鬱)
住宅ローン市場が縮小?
いつもありがとうございます。ansの川瀬です。
今回は住宅市場についてです。
住宅ローンの申し込みにブレーキがかかったようです。さてこの記事、どう見たらよいのでしょうね。
↓↓↓
<住宅ローンしぼむ市場 12月申し込み4.3万件に減少>(2017年1月19日付 日本経済新聞)
【住宅ローン取引の減速が鮮明になってきた。主要8行への申込件数は2016年12月に約4.3万件と日銀がマイナス金利政策を導入する前の水準まで低下。米大統領選後の金利上昇を受けて大手行は17年1月から10年固定の最優遇金利を引き上げており、さらに勢いが鈍る可能性がある。(中略)住宅市況の変調がいよいよはっきりしてくれば投資を控える動きも懸念される。景気への影響も懸念される。】
2016年12月の住宅ローンの申込件数が激減したとのことです。
この調査は三菱東京UFJなど3メガバンクと三井住友信託、りそな、さらに住信SBIネット銀行などインターネット専業3行の取引を集計したものなので、住宅ローンのすべてというわけではありませんが、傾向を見るには十分なものだと思います。
この要因はやはり「住宅ローン金利が上がってきたから」でしょうね。
2016年9月に日銀が金融緩和の姿勢を少し変える方針を出して以降、11月12月とほんの少しではありますが、各行は住宅ローン金利を引き上げました。どうやらそれで申込件数が減少したのでしょう。
記事によると『2015年(H25年)に月平均4万件程度で推移していた住宅ローンの申込件数は、日銀がマイナス金利政策を導入した直後の2016年(H28年)3月には8万件に倍増した』そうです。
それが先月の12月にまた4万件程度まで落ちたということですね。
さて、記事にあるように、これが「住宅市況の変調」の始まりで「景気への影響も懸念される」事態になるのでしょうか?
私見ですが、「今のところ」景気への影響は懸念するほどではないでしょう。
まず、この住宅ローンの申込件数の落ち込みは住宅市況の変調ではありません。国土交通省から毎月発表されている新設住宅着工棟数を見ると、住宅の新築は依然として好調に増えています。新しく住宅を取得して住宅ローンを組むであろう「持ち家」と「分譲住宅」の合計戸数はだいたい月4.5万戸前後で、ここしばらく安定的に推移しています。
そもそも新築着工棟数が月4.5万戸程度なので、住宅ローンの申込件数が4.3万件になったと言われても「そりゃそうでしょ」ということになります。むしろピーク時には住宅ローンの申し込みが8万件もあったことの方が驚きです。
これはどういうことがというと、これまでの住宅ローン申し込みの半数近くは既存の住宅ローンの借り換えだったということでしょう。つまり、この記事が意味するところは『高い金利から低い金利への住宅ローンの借り換えの駆け込みが金利の上昇とともに終わった』ということです。
借り換えは、住宅ローンを高い金利から低い金利に切り替えただけですからほぼ景気やGDPには影響を与えません。銀行の利息収入が少しだけ減って、その分家計が少し助かるだけです。しぼんだのは「住宅ローン市場」であって、「住宅市場」ではないのです。
今のところ、ですが。
住宅業界では、2019年10月に予定されている消費税の10%への増税に向けて、その直前(だいたい2019年3月頃)に駆け込み需要があるのではないかと見る向きがあります。しかし、ここ最近、すでにずっと住宅需要は高いのです。
本来なら今ごろの着工はもっと落ち込んでいると数年前には予測されていました。それは一次取得者層といわれる20代後半から30代後半くらいの層が、人口も世帯数も減少しているからです。
住宅購入世代の人口が減っているのに着工戸数は減っていない(むしろ増えている)。
つまり今、すでに需要の前倒しが起きている、ということなのかもしれませんね。この前倒しを後押ししている要因のひとつは「低金利」であることは間違いないでしょう。もし今の金利上昇傾向が今よりももっと鮮明になれば、逆に今以上の「金利上昇前の駆け込み」が起きるかもしれません。消費増税の2019年を待たずして。
そしてその後に反動の落ち込みがあるでしょう。その時には景気への影響も出るでしょうね。
さて、金利はどう動くのでしょうね。まだまだ日本は低金利政策をとっていますので急激な上昇はないと思いますが、こればかりはわかりません。
注意深く見ておきましょう。
(ハッピーリッチ・アカデミー カワセ君のコラム260号 2017年1月24日付を再構成しました)
新しい投稿ページへ古い投稿ページへ