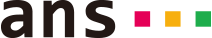未分類カテゴリー記事の一覧です
ansサマーフェスティバル最終日☆
こんにちは!
3連休のansイベント、【ansサマーフェスティバル】もいよいよ



連休最終日はぜひans帯山店に遊びに来てください(≧▽≦)
スタッフ一同お待ちしております!
元気です
いつもありがとうございます。ansの川瀬です。
ブログの更新を1か月以上もサボってしまいました。すみません・・・。
地震が起きて以降、気軽にブログを書けなくなってしまい、気が付いたら1か月以上間を空けてしまいました。
熊本はまだまだ大変な状況にある方が多くいらっしゃいます。「損壊した住宅の建て替えとか修理とかは進んでいますか?」と県外の方から尋ねられることがありますが、全然まだまだこれからです。いまだに片づけも進んでいない家がとても多く残っています。
最近は豪雨が続いています。屋根が損傷しているお家では雨漏りなども起きているようです。これから夏の台風シーズンですが、どうか熊本は避けて通ってもらいたいと願うばかりです。
それでも、熊本の皆さんは力強く復興に向けて進んでいます。表情も明るくなってきたように感じます。
私もとても元気です。相変わらず全国を移動していますし、日曜はansで勉強会の講師もしています。
サボらずにブログも書いていこうと思います。取るに足らないようなくだらないことも書くかもしれませんがお許しください。
暑い日が続きます。体調には十分お気を付けください。
消費増税延期!
いつもありがとうございます。ansの川瀬です。
消費増税についてメルマガを書きました。ご参考になれば幸いです。
『消費増税延期!~社会保障の充実と財政再建は先送り?~』
(ハッピーリッチ・アカデミー245号 平成28年6月3日配信)
6月1日に安倍総理が消費増税を2年半延期することを発表しましたね。
↓↓↓
<首相、消費増税延期を発表 19年10月に10%>
(平成28年6月2日付 日本経済新聞)
『安倍晋三首相は1日、首相官邸で記者会見し、消費税の税率10%への引き上げを2019年10月まで2年半先延ばしすることを表明した。新興国経済の落ち込みなど世界経済の下振れリスクを挙げ「リスクには備えねばならない」と指摘。世界経済が新たな危機に陥ることを回避するため、政策総動員が必要だと強調した。』
サプライズ、ではないですね。
ここ数か月の世の中の雰囲気を見て、多くの方が「延期するんだろうな~」と思っていたと思います。
GDPの伸びはほぼないし、景気は足踏み状態と言えます。中でも肝心の消費が回復していません。
「消費を増やすのが景気回復の鍵」と言われているのに、このタイミングで消費を冷え込ませるような消費増税をやってしまっては、景気の腰が折れてしまいかねません。
世論調査でも大体6割以上の人が増税に反対していました。
現時点では増税延期は妥当な判断だと思います。
■社会保障と財政の問題は先送り、次は大丈夫?
ただ、安倍総理の説明はちょっと苦しかったですね。
新興国など世界経済のせいにしていましたが、明らかに苦しい。前回の延期時に安倍総理は「次は絶対に上げる。景気条項も付けません。」と高らかに宣言していましたので、今回の延期は完全に公約違反です。7月の参院選のこともあって「結局アベノミクスは失敗だったのでは?」という議論も避けたいところでしょう。
「景気が良くなっていないので延期します」とはっきり言えない状況にあるのは何ともお気の毒なことでした。
しかし、次の2年半後の2019年10月末には本当に上げられるでしょうか?
今回の延期で消費税を上げるハードルはかなり上がってしまったと思います。
確かに、今は消費は伸び悩みGDPの成長率も芳しくありません。一方で雇用は順調です。求人倍率は全国でずっと1倍を超える「人手不足」状態ですし、失業率もほぼ完全雇用と言える3%前半という低い水準です。景気は足踏み状態とは言え、決して最悪の状況ではありません。
これで増税出来ないとなると、「ホントに次は大丈夫だろうか…?」と思ってしまいますね。
消費増税はいずれはやらないといけない、というのは大方の合意事項だと思います。
なぜなら社会保障の充実を財政健全化が必要だからですね。
今回の延期で1.3兆円の予算を見込んでいた保育や介護への財源がなくなりました。それでも安倍総理は「一部は実施する」と言っています。財源は赤字国債ではなく、今年の税収増加分を使うとのこと。
確かに今年の所得税収は増えるようです。17.7兆円という14年ぶりの高水準になる、という発表がありました。ただし、この財源は一時的なものです。今回の延期で社会保障制度の充実と財政健全化が遅れるのは間違いありません。
■「消費税より相続税・所得税」という議論
今回の消費増税延期の報道を受けて、「やはり逆進性のある消費税ではなく、富裕層への相続増税とか高額所得者への所得増税をして格差をなくさないといけない」と主張している評論家の人などがいました。
相続税の増税も高額所得者への所得税増税もここ数年ですでに実施されています。
相続税は今年から基礎控除額が引き下げられ、実質的にかなりの増税になっています。所得税についても高額所得者に対する所得控除額が段階的に引き下げれます。これも増税になっています。所得税の増税は住民税や社会保険料にも及びますので高所得者の方の負担は結構増えています。サラリーマンについて言えば、すべての方の厚生年金保険料が毎年徐々に引き上げられており、平成30年まで続くことが決まっています。
取れるところから取る、というのはもうずっとやっています。これ以上の富裕層への課税強化には富の流出など弊害も懸念されています。
「なぜ消費税でないとダメなのか?」というと日本は少子高齢化で生産年齢人口(15歳以上~65歳未満)が減り続けていくからですね。働いて稼ぐ若い人が減っていく、年金・医療・介護費用がかかる高齢者は増えていく。
高齢者の方々にも一定の負担をしてもらうという意味では消費税がいいということになります。
■低成長経済は日本の構造的な問題、では私たちはどうする?
個人消費が伸びていないのも少子高齢化の要因はあると思います。
「消費が伸びないのは賃金が増えないからだ」という指摘がありますが、賃金の総支給額が伸びないのは比較的高所得なベテランが大量に退職しているという世代交代も原因のひとつです。
今、退職している65歳前後の人口は一年代あたり大体200万人です。今、就職しているような20歳前後は120万人くらいです。その差、年80万人。
すごい勢いで働ける人たちが減っています。就労人口でいうと毎年約20万人の働き手が減っているそうです。
高齢世帯は老後に備えて貯蓄をして、若者にはお金がありません。しかも40代50代でゆとりのある高額所得世帯へは毎年増税です。
これでは消費の担い手がいません。なかなか日本は大変ですね。
日本は少子高齢化と成熟した低成長経済の国になっています。これは構造的な問題であり、政治だけで解決できる問題ではありません。
社会保障の充実も財政再建も財源が必要です。財源はないところからは取れません。結局、最後は経済を大きくするしかないのですが、今の日本で経済を大きくするのは簡単なことではないのです。
国民全員が頑張って稼いで、消費をして、貯蓄して、納税もしないといけない。社会が悪いとか誰々が悪いという前に「自分が頑張らねば」と思うのです
是非、参院選に向けては与党、野党ともに足の引っ張り合いやごまかしではない建設的な議論をしてもらいたいですね。
(ハッピーリッチ・アカデミー 245号より)
二重ローンを回避する制度
いつもありがとうございます。ansの川瀬です。
先日メルマガ(4月26日付)で「二重ローン」について書きました。ご参考になれば幸いです。
『熊本地震、二重ローン問題を回避する制度があります』
~自然災害による被災者の債務整理に関するガイドラインとは?~
(ハッピーリッチアカデミー242号 平成28年4月26日付配信)
住宅が損壊し、今も避難生活をおくっておられる方々の中には「まだ先のことは何も考えられない」という方も少なくないと思います。まず今は生活基盤を取り戻すことが優先です。
生活基盤の第一は「住居」です。
当面の住宅の確保について安倍首相は「全体で9,000戸の公営住宅などを確保し、仮設住宅も3,000戸分の資材を確保している」と述べました(4月25日付日経新聞)。
住宅の建て替えや修繕などに対する支援施策は今後徐々に具体的になってくると思います。その中でも特に悩ましいのは「まだ住宅ローンが残っている家が住めなくなってしまった時」だと思います。
地震で家が損壊してしまっても住宅ローンは残っています。被災した方々は住めなくなった住宅ローンを支払い続けながら仮の賃貸住宅に住んだり、新しい住宅を建てるために新たな住宅ローンを組んだりしないといけないのでしょうか。
この住宅に関する二重の負担のことを「二重ローン問題」と言います。
阪神淡路大震災や東日本大震災の時にもクローズアップされ社会問題化しました。
この二重ローンの問題に関して、この4月から新しい制度が始まっています。「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」と言いまして、全国銀行協会が中心となってまとめてました。時間のかかる法的手続きをともなう破産や倒産ではなく、迅速に債務整理をする枠組みになります。
今回の熊本地震がこの新しい制度で被災者を救済する初めてのケースになります。
今現在、定まっている手続きについて全国銀行協会のHPの内容を抜粋・要約して記載します。
「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」の手続きについて
http://www.zenginkyo.or.jp/article/tag-i/8815/
「債務整理のための手続の流れ」
(1)手続着手の申出
「まずローンを借りている金融機関等へガイドラインの手続着手を希望することを申し出ます。金融機関等から借入先、借入残高、年収、資産(預金など)の状況などをお聞きしますので、お手元に借入れの状況などの資料をご用意ください。必要な事項をお聞きし終えた日をもって、手続着手の申出日になります。」
(2)専門家による手続支援を依頼
「要件が確認されて対象となると判断されたら、手続きが始まります。次は弁護士など「登録された専門家」(以下「専門家」)に支援を依頼します。具体的には、地元弁護士会などを通じて「専門家」手配を依頼します。
(3)債務整理(開始)の申出
金融機関等に債務整理を申し出て、申出書のほか財産目録などの必要書類を提出します。書類作成が難しい場合には紹介された「専門家」の支援を受けることができます。債務整理の申出後は、債務の返済や督促は一時停止となります。
(4)「調停条項案」の作成
「専門家」の支援を受けながら、金融機関等と債務整理の内容を協議して、その内容を盛り込んだ「調停条項案」の書類を作成します。
(5)「調停条項案」の提出・説明
「専門家」を経由して、金融機関等へガイドラインに適合する「調停条項案」を提出・説明します。金融機関等は1ヵ月以内に同意するか否か回答します。
(6)特定調停の申立
すべての借入先から同意が得られた場合、簡易裁判所へ特定調停を申し立てます。
(7)調停条項の確定
特定調停手続により調停条項が確定すれば債務整理成立です。
調停なんて単語が出てくるとわからなくなってしまうかもしれませんが、詳しい手続きは弁護士さんなどの専門家がサポートしてくれます。まずは銀行へ行って相談することからです。その際には「罹災証明」も必要になります。まずは今の返済を止めてもらう(3)の段階まではスムーズに行きたいところです。
通常だと債務整理をすると個人信用情報に登録されてしまい、新しい借入が出来なくなりますが、このガイドラインに則った手続きでは登録されません。過去の債務を整理してスムーズに新しいローンを組むことが出来ます。
まだまだ厳しい日々を送っておられる方は多いと思います。どうぞお身体には気を付けください。
どんなことでもご相談ください
いつもありがとうございます。ansの川瀬です。
熊本では今も余震が続いています。まだまだ不安定な状況ではありますが、熊本の皆さんは力強く復興への歩みを始めています。
ansも4月23日よりお店を再開しております。多くの皆さま方よりお心遣いやご心配をいただきましたこと、心より感謝申し上げます。
今、多くの方が住まいに関する様々なことで困っていらっしゃいます。
ansではこれまで住宅の新築のお客様を中心に家づくりのお手伝いをしてまいりました。しかし今は緊急事態です。新築に限らず住まいに関することならどんなことでも構いませんのでご相談ください。私どもでお力になれることがあれば出来る範囲で全力で対応いたします。
ansには住宅・不動産を専門にしている弁護士や、建物の構造や耐震に詳しい建築士、地盤の専門家や住宅ローンの専門家など様々な分野に精通したブレーンがいます。
まずスタッフがお話しをお伺いします。必要に応じて専門家などに確認して迅速にお答えいたします。
一日も早く熊本の皆さんに平穏な暮らしが戻りますよう祈っています。
微力ではありますが、私たちも力を尽くして参ります。
熊本地震、お見舞い申し上げます。
いつもありがとうございます。ansの川瀬です。
昨晩、熊本では大変なことが起きました。
皆さま、大丈夫でしたでしょうか?
被害に遭われた皆さまには心よりお見舞い申し上げます。
ansは帯山、流通団地の両店舗とも被害は軽微なもので、スタッフ全員の無事も確認できております。多くの方にはansのことも御心配いただき、ご連絡をいただきましてありがとうございました。
一日も早く通常営業出来るように動いております。
避難されている方々をはじめ、皆さま不便で不安な時を過ごされていることでしょう。まだまだ余震もしばらく続くようです。どうぞ御身の安全を第一に、お気を付けてお過ごしください。
さて消費税、増税か?延期か?
いつもありがとうございます。ansの川瀬です。
少しずつ春めいてきましたね。サクラの見頃がいつになりそうかということが気になります。
さて、気になると言えば、「消費税」ですね。
住宅取得を検討されている皆さまにとっては来年4月に消費税が予定通り10%になるのかどうか、ということは住宅取得スケジュールにも影響しますので大きな関心事だと思います。
安倍総理は、これまでと変わらず「リーマンショックや大震災のようなことが起きない限り予定通り増税する」という姿勢を今のところは崩していません。しかし、ここ最近どうも「増税を延期するのではないか?」というような雰囲気がぷんぷんしてきましたね。
<クルーグマン氏「消費増税、いまではない」>(平成28年3月23日付 日本経済新聞)
『安倍晋三首相が5月下旬の主要国首脳会議(伊勢志摩サミット)の準備会合と位置付ける国際金融経済分析会合は22日、首相官邸でノーベル経済学賞を受賞したクルーグマン米プリンストン大名誉教授を招き、第3回会合を開いた。これまでに出席した有識者からは政府に積極的な財政出動を求める意見が相次ぎ、消費増税の延期論も出た。』
先週には同じくノーベル経済学賞を受賞したコロンビア大のスティグリッツ教授も同じ会合に出て「増税は今すべきことではない」と話しています。アベノミクスの仕掛け人である浜田宏一氏や本田悦郎氏もテレビや新聞、本、雑誌などで「消費増税見送り」を繰り返し主張しています。
今、日本の企業業績は決して悪くないし、雇用状況はかなり良くなっています。景気は明らかに上向きつつありますが、それでもGDPが成長していない一番の要因は、消費や投資が伸びていないからですね。だから、政府は企業に対して賃上げや投資促進を要請しているわけです。
景気の本格回復を抑制している要因が「消費が伸びていないこと」だとすると、消費を増やす政策こそが今なすべきことであり、消費増税はその真逆の政策なのでやるべきではない。浜田・本田両内閣官房参与やクルーグマン先生らが言っていることは要するにそういうことです。
確かに、消費増税したら間違いなく消費は今よりさらに落ち込みます。今の弱々しい経済状況ではまたまたデフレに逆戻りする可能性は高いでしょう。
野党の民主党は「増税延期はアベノミクスの失敗であり、安倍政権の敗北である。」(細野豪志政調会長)と攻撃しています。(増税して景気が悪くなってもまた同じことを言うのでしょうけど・・・)
さて、増税か?延期か? どうなるでしょうね。
7月には参院選があるので、伊勢志摩サミットの後の6月上旬ごろには方針が出るのではないかなと思います。
空き家問題、施策を理解して早めの対策を
いつもありがとうございます。ansの川瀬です。
空き家についてメルマガに書きました。ご参考下さい。
(ハッピーリッチメルマガ238号より http://www.happyrich.jp/columns/238.html)
----------------------------------------
■空き家の何が問題か?
空き家が増えて問題になっています。
総務省の調査によると全国の空き家総数は約820万戸。空き家率(住宅全体に占める空き家の割合)は13.5%。いずれも過去最高水準に達しています。野村総合研究所は、空き家の転用が進まなかった場合には、20年後には空き家率は30%を超えると推計しています。
今、日本は人口も世帯数も減っていますので空き家が増えるのは仕方がありません。ただ、だからといって空き家を放置しておくことは社会的な損失を増やすことになりますので避けねばなりません。
誰も住まない家は劣化のスピードが早くなります。劣化した廃墟のような家は街並みの景観を悪くするだけでなく、ゴミが不法投棄されたり、不法侵入されて犯罪の温床になる可能性もあります。火災も心配です。最終的に建物の撤去・解体を自治体がしなければならなくなると財政への負担も増えます。国土交通省はこういった廃墟のような管理されない不動産の増加は「周辺住民に不利益をもたらす」としています。
では、皆さんが実家の相続などで空き家の所有者になってしまった場合、どのように対応すればよいのでしょうか?
■空き家は固定資産税が6倍になることも
結論から言いますと、自分も家族もその空き家を利用する予定がないのであれば、早めに売却を考えるのが無難です。
空き家は所有しているだけで費用がかさみます。固定資産税や都市計画税も、家が建っているので軽減されているとは言え一定額が毎年かかりますし、水道・光熱費や火災保険料、定期清掃などの管理の経費もかかります。こうした費用は年間数十万円にもなります。
昨年、空き家を放置しないための施策が打ち出されました。住宅用地の固定資産税は6分の1に軽減されていますが、市町村などの自治体が「特定空き家」と認定すると軽減の対象外になります。固定資産税が6倍になるわけです。
さらに「倒壊の恐れがある」とされますと修繕や解体の指導がきます。所有者が指導に従わない場合には自治体が強制的に解体を執行することもできるようになりました。その解体にかかった費用は原則所有者の負担です。
空き家のままおいておく減税のインセンティブがなくなり、むしろペナルティが課せられる可能性が出てきたわけです。
■売却を促進する税制改正が4月よりスタート
政府は空き家施策で「アメとムチ」を用意しました。固定資産税6分の1優遇の打ち切りや解体の強制執行などは「放置するな」という「ムチ」ですね。次は「アメ」の施策が今年の4月から始まります。それは『空き家を売却した際の譲渡所得の3,000万円特別控除』です。
譲渡所得とは売却価格からもともとのその住宅の取得費を差し引いたものです。要するに「家の売却益」のことです。通常その売却益に対しては譲渡所得税がかかります。税率は所得税・地方税合わせて20%です。
例えば、ざっくりいうと2,000万円で元々取得した不動産が3,000万円で売れたら利益は1,000万円ですね。そこに20%の譲渡所得税(200万円)がかかります。(5年以内の短期保有の場合の税率は39%)
空き家の場合、取得価格がいくらだったのかわからないくらい古い家が多いのですが、そういった取得原価がわからない場合には譲渡価格の5%を取得費とみなすことになっています。3,000万円で売れたときの取得原価は150万円になります。そうなりますと譲渡所得は2,850万円ですね。
譲渡所得税は2,850万円×20%=570万円。
結構な額を税金として支払わねばなりませんね。これが4月からは、相続から3年以内に限ってですが、譲渡所得3,000万円までは税金がかからなくなります。
譲渡所得の優遇については、もともと自宅の売却時には3,000万円までの控除がありますが、自分が住んでいない空き家は対象外でした。それが今回の税制改正で対象になるのですから「それなら今のうちに処分しておこうかな」となる人も増えるかもしれませんね。
このアメの施策は、特に不動産価格の高い都市部ではそれなりの効果を発揮するのではないでしょうか。4月以降、空き家や更地が売りに出る可能性はあるかもしれませんね。
※適用には様々な条件があります。よくご確認ください。
※適用条件:相続した空き家であること。旧耐震しか満たしていない建物で、相続人が必要な耐震改修または除却を行うこと。
■問題は売りたいけど売れない家・・・
親から相続した上を管理もせずに放置しておくことのリスクはこれまでよりも格段に上がっています。だから税を優遇するので早めに売ったらどうですか、というのが国の施策です。
しかし、この施策で解決できるのは恐らく今の空き家の一部だけだと思います。
約820万戸の空き家のうち賃貸住宅が5割強あります。賃貸住宅は空き家になっても多くは管理がなされているのでそれほど問題はありません。問題は約400万戸ほどある持家の方です。
持家の中でも立地条件が良くてそれなりの値段で売却できるものや、それなりの賃料で貸せるものであればそれほど問題はありません。(そんな良い立地にある家ならそもそも空き家で何年も放置はされないでしょうけどね)
問題は、売りたくても売れない家です。例えば郊外にある老朽化した家のような場合です。売りに出しても買い手がつかないのですから処分ができません。そのまま適切な管理もされずに放置されるうちに劣化が進み資産価値が下がり、ますます売れなくなる。これが廃墟に向かう悪循環です。こういう物件は値段を下げたところでなかなか売れません。
自治体に寄付しようとしても恐らく断られるでしょう。利用価値のない不動産は管理費がかさむだけですからね。自治体としても税金を使ってそんなことはできません。
売りたくても売れない、自治体も誰も引き取ってくれない、そのうちに固定資産税も上がる・・・
八方ふさがりですね。
こういう場合、費用をかけて解体して更地にした上で無償でも引き取ってもらえるかということを早めに考えないといけないと思います。解体費用は持ち出しになってしまいますが、それでも将来にわたって続く所有コストよりも解体費が安く済む計算になるなら選択肢になるでしょう。
国土交通省の調査では空き家の取得理由の過半数が「相続」です。相続した空き家はある程度の費用をかけても相続人が自己責任で何とかするように、という時代が来ています。
「とりあえずもらっておこうかな」という程度の軽い気持ちで相続すると後々大変なコストがかかってしまうかもしれません。市場価値のある空き家はあまり価格にこだわらずに、建物が劣化する前に早めに売却するのがよいかと思います。
今回は以上です。
住宅ローン金利、過去最低に
いつもありがとうございます。ansの川瀬です。
3月になりました。住宅ローンの3月金利が発表されましたね。
日銀のマイナス金利政策が発表されてから住宅ローン金利に連動している10年物国債金利もマイナス水準にまで落ちていましたので、やはり住宅ローン金利も下がりました。
<大手銀行住宅ローン、金利引き下げ相次ぐ>
(平成28年3月1日 読売新聞)
『大手銀行は29日、3月の住宅ローン金利を発表した。三井住友銀行とみずほ銀行、りそな銀行の3行は10年固定型の優遇金利を前月より0.10%下げて、過去最低の年0.80%とした。3行は2月の途中で金利を年0.90%に下げていたが、3月からはさらに引き下げる。三菱東京UFJ銀行も3月から年0.80%に引き下げるため、4行が同水準で並ぶことになった。三井住友信託銀行は年0.50%で、4行よりもさらに低い水準だ。』
「もうこれ以上は下がらないだろう」と言われ続ける中、ずっと下がり続けているローン金利。ついに10年固定が1%切る水準になりました。全期間固定のフラット35の基準金利もまもなく発表されると思いますが、恐らく過去最低の1%近くになると思います。
もうすごいレベルですね。
銀行は全然儲からない水準になっています。
以前も書きましたが、住宅ローン金利が1%を切る水準になりますと、支払う利息額よりも住宅ローン減税の所得税の還付で受け取る額の方が上回る人が多くなります。実質的に「ローンを借りると家計にプラスになる」という「ローンのマイナス金利」状態ですね。
その分、景気回復の足取りも重たいようなので先行きに不安を感じている方も少なくないかかとは思いますが、少なくとも家づくりを考えている方にとっては絶好のタイミングということになります。消費税の増税も気になるところですしね。
さすがに、もうこれ以上は下がらないだろう!・・・と、とりあえず言っておきます。
熊本城マラソン、お疲れ様でした!
いつもありがとうございます。ansの川瀬です。
先週の日曜は熊本城マラソンでしたね。出場されたランナーの皆さま、ボランティアの皆さま、沿道で応援された皆さま、お疲れ様でした。
好天に恵まれた絶好のコンディションの中、ansからも塩崎以下4人のスタッフが出場し、全員(フラフラになりながらも)見事完走いたしました!
おめでとう!
私は2年連続で落選してしまいましたので、今年もans流通団地店前にて応援しておりました。皆さんが走っているのを見るとなんかうずうずしてきますね。
2年前にはansのシャツを着て私も走りました。その時にはまだansもオープンしたてでしたので、ansのロゴを見たお子様に「エーエヌエスってな~に?」と聞かれたりしました。
今年も4人の出場者はみな「ans」のロゴの入ったシャツを着て走りましたが、多くの皆様に「ansさん!ガンバレ~!」とお声がけいただいたようです。
そのansランナーの中に全国のマラソン大会に何度も出場している猛者がいます。彼は「熊本城マラソンの応援やおもてなしはこれまでに出た大会の中でも一番すごかった!これは間違いなく日本一の大会ですね!」と感激しておりました。
「すごいでしょ、熊本。」と私も誇らしい気持ちになりました。応援いただいたすべての皆様に御礼申し上げます。
来年こそは私も走りたいですね。当選しますように!
さて、来年に向けて早速トレーニングに入ります!(嘘)
新しい投稿ページへ古い投稿ページへ