COLUMN

住まいづくりコラム
吹き抜けのある家づくり!魅力と注意点を徹底解説
家づくりを考え始めたとき、「吹き抜けのある開放的な家に住みたい!」と憧れる方は多いのではないでしょうか?吹き抜けは、視線が広がり、光がたっぷり入るデザイン性の高い空間を作れるのが魅力です。しかし、「冬に寒くなりそう…」「2階のプライバシーは大丈夫?」などの不安もありますよね。
今回は、吹き抜けのメリット・デメリット、後悔しないためのポイントなどを詳しく解説していきます!

目次
- ・吹き抜けのメリット
- ・吹き抜けのデメリットと対策
- ・吹き抜けを快適に活用するための設計ポイント
- ・まとめ
《 吹き抜けのメリット 》
①圧倒的な開放感を得られる
吹き抜けの最大の魅力は、空間の広がりを演出できることです。天井が高くなることで、実際の床面積以上の開放感を得られ、家全体が広々とした印象になります。特に狭小住宅や都市部の住宅では、横の広がりが制限されることが多いため、吹き抜けを活用して縦の空間を有効に使うことが重要です。
例えば、リビングに吹き抜けを取り入れることで、限られたスペースでも広がりを感じられ、視覚的なゆとりを確保できます。また、玄関に吹き抜けを設けると、訪れる人に明るく開放的な印象を与えられ、より welcoming(歓迎的)な空間になります。
②自然光をたっぷり取り込み、明るい空間を実現
吹き抜けを取り入れることで、上部に窓を設置しやすくなり、自然光を効果的に室内に取り込むことができます。特に、隣家が近接していたり、日当たりが限られる住宅では、吹き抜けの高窓を活用することで1階の奥まで光が届き、明るく開放的な住環境を確保できます。
さらに、吹き抜けを南向きに設計すれば、冬場は日射熱を活用して室温を上げることができ、省エネ効果も期待できます。一方で、夏場の直射日光が気になる場合は、庇(ひさし)や遮熱ガラスを採用することで、快適な室温を維持しつつ明るさを確保することができます。こうした工夫により、日中の電気代を節約しながら、気持ちのよい暮らしを実現できるのも吹き抜けの大きな魅力です。
③家族のつながりを感じやすく、コミュニケーションがとりやすい
吹き抜けを通じて1階と2階の空間がつながることで、家族の気配を感じやすくなります。例えば、リビングにいる家族の声が2階にも届くため、異なるフロアにいても自然と会話が生まれ、コミュニケーションが活発になります。特に、小さな子どもがいる家庭では、2階の子ども部屋や書斎にいてもリビングの様子が伝わるため、親子の安心感が高まります。また、リビングと2階の空間が緩やかにつながることで、家族が互いに干渉しすぎず、ほどよい距離感を保ちながらもコミュニケーションをとりやすい住まいを実現できます。
④インテリアデザインの自由度が高い
吹き抜けを取り入れることで、住宅デザインの幅が広がり、スタイリッシュな空間を実現できます。例えば、大きな照明やシャンデリアを設置することでラグジュアリーな雰囲気を演出したり、木材を活かしたナチュラルなデザインにしたりと、住まいの個性を際立たせることができます。さらに、吹き抜け部分に室内窓を設けることで、デザイン性を高めながら光や風を効果的に取り込むことも可能です。特に、ガラスやアイアンフレームを取り入れた室内窓は、おしゃれなアクセントとなるだけでなく、住空間のつながりをより強調し、モダンな印象を与えます。
《 吹き抜けのデメリットと対策 》
①冷暖房の効率が悪くなる

吹き抜けは空間が広くなるため、冷暖房の効率が下がるという問題があります。特に冬場は暖気が上へ逃げてしまい、足元が寒く感じることが多くなります。また、夏場は冷房の冷気が下に溜まりやすく、上部の空間が蒸し暑くなることがあります。
■対策
・床暖房や蓄熱暖房を活用する
床からじんわりと暖めることで、足元の寒さを軽減できます。蓄熱暖房を取り入れると、夜間に熱を蓄え、日中の寒さを和らげる効果も期待できます。
・シーリングファンを設置する
吹き抜けの上部にシーリングファンを設置することで、暖かい空気を下へ送り、室内の温度差を小さくできます。夏場は逆回転(風を上へ送る)にすることで、冷房の効率も向上します。
・高断熱・高気密の住宅にする
断熱材を強化することで、室内の温度を一定に保ちやすくなります。発泡ウレタンやセルロースファイバーなどの高性能な断熱材を使用すると、より効果的です。また、窓の断熱性能を高めるために、Low-E複層ガラスやトリプルガラスを採用し、サッシを樹脂やアルミ樹脂複合にすることで、熱の流出を防ぐことができます。
・エアコンの配置を工夫する
吹き抜けの上部にもエアコンを設置することで、空間全体を効率よく冷暖房できます。さらに、サーキュレーターを併用することで、エアコンの風をうまく循環させ、快適な室温を維持しやすくなります。
②音が響きやすい

吹き抜けは1階と2階をつなぐ開放的な空間のため、音が上下に伝わりやすくなります。特に、リビングが吹き抜けになっている場合、2階の子ども部屋やワークスペースにリビングのテレビの音や会話が響くことがあります。逆に、2階の足音や話し声が1階に聞こえやすいという問題もあります。
■対策
・吸音材やカーペットを活用する
壁や天井に吸音パネルを設置することで、音の反響を抑え、室内の騒音を軽減できます。また、カーペットやラグを敷くことで、足音の響きを和らげることができます。さらに、遮音シートを床に施工することで、2階からの生活音が1階に伝わりにくくなります。
・間仕切りを設ける
開閉式のパーテーションを設置することで、必要に応じて空間を仕切り、音を遮断できます。吹き抜け部分に室内窓を設けることで、音の通りを和らげつつ、開放感を維持することが可能です。
・家具の配置を工夫する
壁側に本棚や収納を設置することで、音を吸収しやすくなり、防音効果が期待できます。また、吸音効果のあるカーテンを取り入れることで、音の反響を抑え、快適な空間を作ることができます。
③メンテナンスが大変

吹き抜け部分の窓や照明は高い位置にあるため、掃除やメンテナンスが難しくなります。特に、高窓はホコリや汚れが溜まりやすく、定期的な掃除が必要になります。しかし、手が届かないため、掃除のたびに脚立を使うなどの手間がかかります。
■対策
・掃除しやすいデザインを選ぶ
開閉可能な窓を設けることで、内側から簡単に掃除できるようになります。また、ホコリがたまりにくいシンプルなデザインを意識することで、日常の掃除がしやすくなります。
・リモコンで操作できる照明を導入する
昇降式のペンダントライトを設置することで、高い位置の照明のメンテナンスが楽になります。さらに、LED照明を採用することで、電球交換の頻度を減らし、手間を軽減できます。
・掃除用の設備を取り入れる
2階部分にキャットウォークを設けることで、高窓の掃除が簡単になります。また、高所掃除用の延長ポールを活用することで、手の届かない場所の掃除がしやすくなり、メンテナンスの負担を軽減できます。
《 吹き抜けを快適に活用するための設計ポイント 》

①吹き抜けのサイズを適切に設計する
吹き抜けの面積が大きすぎると、冷暖房効率の低下や音の問題が強調されるため、バランスを考慮することが重要です。リビングの一部を吹き抜けにすることで、適度な開放感を確保しつつ、デメリットを軽減できます。 また、廊下や階段部分に吹き抜けを設けることで、自然光を取り入れながらも、冷暖房の影響を抑える工夫ができます。
②適切な窓配置を考える
吹き抜けに設置する窓の配置によっては、日射の影響が大きくなるため、適切な遮熱対策を考慮することが必要です。南向きに高窓を設置すると、冬場の採光を効果的に得ることができます。一方で、夏場の直射日光を防ぐために、庇(ひさし)や遮熱カーテンを活用すると、室温の上昇を抑えられます。また、通風を考慮し、上下に窓を設けることで、空気の流れを作り、快適な室内環境を維持しやすくなります。
③ 断熱性能を向上させる
吹き抜けを取り入れる場合は、家全体の断熱性能を高めることで、快適な住環境を確保できます。そのために、高性能な断熱材を使用し、窓の断熱性能を向上させる(Low-E複層ガラスやトリプルガラスを採用する)ことが効果的です。さらに、全館空調を導入することで、家全体の温度を均一に保ち、吹き抜けによる温度差を抑えることができます。
《 まとめ 》
吹き抜けのある住まいは、開放感や採光性など多くの魅力を持つ一方、冷暖房効率や音の響き、メンテナンスといった課題も伴います。これらのメリットとデメリットを十分に理解し、適切な設計と対策を講じることで、快適で後悔のない住環境を実現できます。
住まいづくりに関する疑問や不安をお持ちの方は、ぜひ「住まいづくりの出発店ans(アンズ)」の無料個別相談会や勉強会にご参加ください。ansでは、専門のアドバイザーが資金計画、土地探し、住宅会社の選び方など、住まいづくりに関するあらゆるご相談に対応しています。一緒に、理想の住まいを実現しましょう!
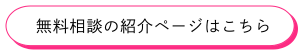
![熊本・静岡の住まいづくりの出発店[アンズ]](/img/logo.png)


