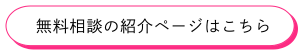COLUMN

住まいづくりコラム
災害に備える「安心して暮らせる家」を考える5つの視点
最近、地震・台風・豪雨など自然災害のニュースが絶えません。
「いつ」「どこで」起きても不思議ではない今、家を建てる場所や構造をしっかり考えることが、家族の命と暮らしを守る第一歩になります。
今回は、これから家を購入・建築する方に向けて、“災害に強い家”を考える上で意識したい5つの視点をご紹介します。
目次
- 1.地盤や浸水リスクを調べよう!
- 2.台風に強い構造とは?
- 3.地震に強い家とは?
- 4.停電・断水への備えは?
- 5.災害時も避難しやすい立地とは?
- まとめ
《 1.地盤や浸水リスクを調べよう!》
土地探しの際に必ずチェックしてほしいのが「ハザードマップ」。
海のある県に住むなら、津波のハザードマップなら一度は見たことがあるのではないでしょうか。
ハザードマップは津波以外にも、大雨の際の洪水や河川の氾濫、土砂災害などの情報も見ることができますが、同じ町内でも土地の起伏や形状によって浸水深が違う場合もあるので、過去の浸水履歴も含め、気になる土地があれば都度調べてみると安心です。
また地盤の強さも、地震の震度や沈下・液状化にも影響する重要な要素です。
分譲地でもAの土地の地盤が良かったからと言って隣のBの土地も良いとは限りません。
購入前に地盤調査をすることは通常できませんが、気になる土地がどんな地質でできているか、昔はどんな地形だったのかを知っておけば、地盤強化の費用を予め予算取りしておくこともできますし、災害リスクを減らすことは可能です。

《 2.台風に強い構造とは?》
台風の暴風や飛来物から住まいを守るには、構造そのものの強さが大きなポイントになります。
現代の住宅の強度であれば、3匹のこぶたのワラのお家のように吹けば飛ぶと言うことはありませんが、特に屋根・外壁・窓まわりの仕様によって、被害の大きさは大きく変わってきます。
まず屋根材は、軽くて耐久性のある素材を選ぶことで、飛散や落下のリスクを軽減できます。
最近では防災瓦と呼ばれる瓦もあり、風圧に強く、耐久性も高いと言われています。
外壁についても、耐衝撃性や耐風圧性に優れた材質を選ぶことで、飛来物による損傷を最小限に抑えられます。
タイルはメンテナンス性が高く人気ですが、飛来物で割れやすいものもあります。
窓は住宅の中でも特に風や飛来物の影響を受けやすい箇所。
そこで有効なのが、耐風性能に優れたガラスやシャッターです。
昔は雨戸や格子で見た目でもわかるような対策が主流でしたが、最近の防犯合わせガラスなら飛来物で割れても破片が飛び散りにくくなっているので安全ですし、電動シャッターや高性能な飛散防止フィルムも普及してきており、防災対策と見た目の両立も可能になっています。
また、災害時に頼りになるのが「メンテナンスのしやすさ」です。
長年使う住まいだからこそ、被害を受けたときに点検や修理がしやすい構造かどうかも事前に確認しておくと安心です。
《 3.地震に強い家とは? 》
TVCMでも「地震に強い」ことをアピールしている住宅会社さんは多いですが、地震が多い日本では、家の耐震性は命を守る重要なポイントです。
「木造=地震に弱い」と思われがちですが、しっかりとした構造計算と設計によって、十分に地震に強い家を建てることができます。
また、建物自体を地震の揺れに強くすることを「耐震」と言いますが、地震対策としては、揺れを吸収する装置を壁内の適所に設置する「制震」、建物の下に装置を入れて揺れを建物に伝えにくくする「免震」があります。
コスト面からすると免振装置を入れることが一番高額のため、家の耐震性を高める設計や構造を取り入れることが一般的ですが、耐震性を高めた上で制振装置を標準仕様で取り入れる会社さんも多くなってきました。
さらに万が一の対策として、地震保険や転倒防止策で備え付けの家具を検討することも、住んでいる間の安心に繋がります。
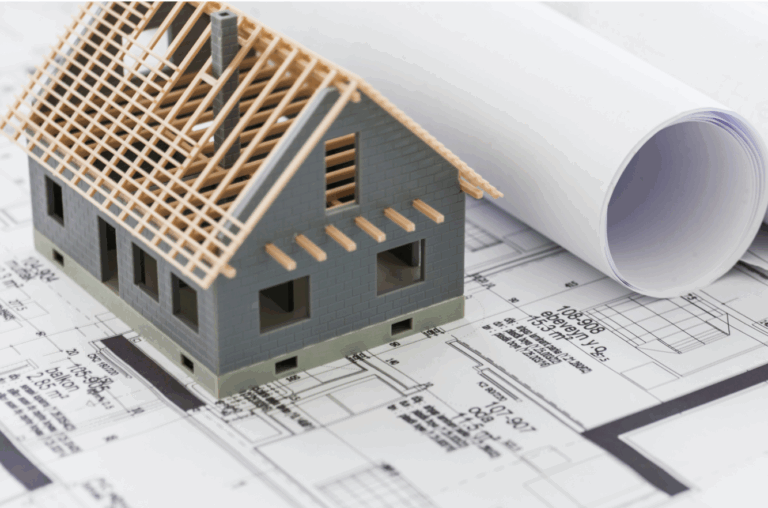
《 4.停電・断水への備えは? 》
台風や地震など災害のあと、数日間も停電や断水が続くケースも少なくありません。
そうした非常時のためにまず検討したいのは、太陽光発電+蓄電池の導入です。
日中に発電した電力を蓄電池にためておくことで、停電時にも照明や冷蔵庫、スマホの充電など最低限の生活を維持できます。
災害に強い家にはなりますが、初期費用も安くはないため、その分の費用も予め予算取りしておくことが重要です。
次に、非常用の水とトイレの備えも忘れてはなりません。
給水ポリタンクや携帯トイレを備えるのはもちろんのこと、建物の間取りに「備蓄スペース」があるかどうかも大切な視点です。
たとえば、床下収納やパントリー、シューズクロークなど、水や保存食、生活用品をストックしておける場所を設計の段階で確保しておくと安心です。
災害に備える家づくりとは、特別な設備を追加するだけでなく、日常生活の中で無理なく備えを続けられる環境を整えることでもあります。

《 5.災害時も避難しやすい立地とは? 》
災害時に命を守るためには、家の性能だけでなく立地や設計の工夫も欠かせません。
避難しやすさを左右するのは、普段あまり意識しない“まわりの環境”や“家の中の動線”です。
たとえば、道路との高低差が大きい土地では、浸水時に逃げ遅れるリスクがあるため注意が必要です。
また、住宅が密集しているエリアでは、災害時に火災の延焼や、避難路がふさがれて移動が困難になる場合もあります。
また引越したばかりで土地勘が無い場合もスムーズな避難の妨げになりますので、引越したら早めに自宅から避難場所までの地理を家族と共有しましょう。
さらに、家の中にも「避難のしやすさ」は設計できます。
寝室の近くに避難用の靴を置いておくスペースをつくったり、夜間の避難の動線はセンサーライトにしておくといった工夫も、設計段階の備えとして有効です。
「災害時、どうやって家から安全に出られるか?」
そんな視点で、土地選びや家の間取りを考えてみることが大切です。

《 まとめ 》
地震や台風、大雨など、日本では自然災害のリスクを完全に避けることはできません。
でも「災害はいつ起こるか分からない」からこそ、“備えること”は誰にでもできます。
とはいえ、災害への備えに強い家を、どこで建てられるのか、自分たちに合った住宅会社はどこなのか、不安や迷いがある方も多いはずです。
私たちは、そうした不安や疑問を整理しながら、信頼できる住宅会社をご紹介しています。
「災害に強い家」をキーワードに、自分たちらしい暮らしを叶えたい方、まずはお気軽に無料相談会にお越しください。
【関連記事】
・地盤改良に100万円超!?家を建てる前に知っておくべき出費と対策
・ハザードマップで浜松市を徹底チェック!水害に強いエリアと住まいづくりのコツ
・ハザードマップで見る、熊本市で水害のあるエリアは? 注文住宅を建てる際のポイントとは?
![熊本・静岡の住まいづくりの出発店[アンズ]](/img/logo.png)